「備蓄米が放出されたって聞いたのに、全然どこにも売ってない…」
「スーパーや通販を見ても在庫なし、なんで?」
そんな声がSNSでも広がっています。政府の備蓄米が放出されたというニュースを見て、「じゃあ備蓄用のお米が手に入る!」と期待したのに、どこを探しても見つからない…。実はこれには、見えない流通の仕組みと、誤解されがちな“放出”の意味が関係しているのです。
この記事では、「備蓄米が放出されたのになぜ買えないのか?」を徹底解説し、本当に買える場所や、現実的な備え方のヒントもわかりやすく紹介しています。
災害への備えに悩むあなたに、実践的で安心できる情報をお届けします。
備蓄米が“放出された”ってどういう意味?
ニュースで言われた「放出」の正体とは
最近、「政府の備蓄米が放出された」というニュースを耳にした方も多いのではないでしょうか。「放出」と聞くと、「一般家庭でも買えるようになったのかな?」と思ってしまいがちですが、実際のところ、その意味は少し違います。
ここでいう「放出」とは、政府や自治体が災害対策などのために保有している米(政府備蓄米)を、一定の期間を過ぎたり在庫が余ったりした際に市場に売却する(民間流通に回す)ことを指します。つまり、「今まで封印されていた備蓄米を誰でも買えるようにした」というわけではなく、特定の条件下で、一部の業者向けに販売が始まったという意味合いが強いのです。
多くの場合、この備蓄米の放出は、農林水産省や地方の農政事務所が入札制度を通じて実施します。購入できるのは、米の取り扱い実績がある業者や加工業者など、一定の資格を持つ法人が中心です。一般の消費者がスーパーや通販サイトで直接手に入れられるような形では、基本的に販売されていません。
そのため、「放出された=すぐ買える」という印象を持つと、実際の流通状況との間にズレが生じ、「どこにも売ってない!」と戸惑ってしまうわけです。
国や自治体が保有する備蓄米とは?
そもそも「備蓄米」とは何なのか。その正体は、国が管理している**「政府備蓄米」と、地方自治体や企業が災害に備えて備蓄している「民間備蓄米」**の2種類があります。
政府備蓄米は、食料安全保障の観点から国が計画的に保有しているお米で、常に数十万トン規模が備蓄されています。主に自然災害や国際的な食料危機など、非常時に国民の食を守るための最後の手段として活用されるものです。
一方で、自治体や企業が保有している備蓄米は、学校給食や避難所、施設向けに使われることが多く、地域単位で管理されています。最近ではアルファ化米やレトルトパックタイプなど、長期保存が可能で調理が簡単な商品が主流になっています。
ただし、これらの備蓄米は日常的に流通しているわけではなく、災害時や入れ替え時期(賞味期限が近づいたときなど)にのみ、市場に一部出回ることがあります。この「一部出回る」タイミングが、いわゆる「放出された」という表現の背景です。
放出された備蓄米はどこに向かうのか
放出された備蓄米がすぐに一般向けに売られるわけではありません。実際には、業務用ルートや加工用として使われることがほとんどです。
たとえば、学校給食、病院、老人ホーム、外食チェーンの業者が入札で落札し、自社の調理現場で使用したり、おにぎりやお弁当の製造に使ったりします。また、一部は家畜の飼料用や米粉として再加工される場合もあり、すべてが「そのままごはんとして家庭で食べられる」状態ではないのです。
加えて、放出された米は「古米(こまい)」や「古古米(ここまい)」と呼ばれる、収穫から1年以上経過したお米であることが多く、風味や粘りが劣るため、家庭用としてはあまり向かないと判断され、一般販売に回されないことが多いです。
つまり、放出された備蓄米は主にBtoB(業者向け)の流通に乗るため、私たちの生活の中で直接その姿を見る機会はほとんどないのが現実です。
なぜ一般消費者の目に触れないのか
多くの人が「放出されたのになぜスーパーで見ないの?」と疑問に思うのは当然です。ですが、その背景には、備蓄米の放出自体が業者を対象にしたものであり、販売ルートが完全に分かれているという構造があります。
業者は大量に購入し、加工や業務利用を前提に使うことがほとんどで、小分け販売の手間やコストをかけて一般向けに流通させることは稀です。さらに、こうした放出米はパッケージも簡易的で、賞味期限も短いため、小売店が「一般向け商品として並べるにはリスクがある」と判断して仕入れないのです。
結果的に、放出された米は市場に出回ってはいても、私たちの目に触れる場所には存在しない=見かけないという状態になってしまいます。
放出=一般販売ではない現実
まとめると、「備蓄米が放出された」という言葉が指すのは、在庫処分や賞味期限切れ前の売却(BtoB)であり、BtoC(私たち個人消費者)向けではないということです。
そのため、「放出されたのになんで買えないの?」という疑問は正しく、でもその答えは、「そもそも私たちには回ってこない流通構造になっているから」なのです。
この記事の続きでは、実際に備蓄米が買える場所や探し方を紹介していきます。
スーパーや通販で見かけないのはなぜ?
流通ルートが通常の商品と異なる
備蓄米が放出されたと聞いて、「じゃあ近所のスーパーやネットショップを見れば売っているはず」と思う方は多いでしょう。ですが、放出された備蓄米の多くは、通常の食料品と同じルートを通っていません。ここが一番の落とし穴です。
スーパーや楽天・Amazonといった一般向けの流通網は、メーカーや問屋が商品を企画し、小売店が仕入れて販売するというルートです。しかし、備蓄米の放出は、農林水産省などの行政機関が主催する**「入札方式」や「限定販売」**が基本。対象となるのは大口購入が可能な法人や業者です。
このため、一般の小売業者が仕入れようと思っても、数量・資格・契約条件などのハードルが高く、参加できないケースも多いのです。さらに、入札に参加できたとしても、品質や保存期間の問題から、小売店では扱いづらいと判断されがちです。
つまり、放出米が存在しても、それが自然とスーパーや通販の棚に並ぶような構造にはなっていないということです。これは制度的な問題というより、流通の仕組みそのものが「業者向け」に最適化されているからなのです。
一般消費者向けに出回る量がごくわずか
もう一つの理由は、そもそも放出される備蓄米の量が少ない上に、一般向けに回る分はさらに限られているということです。
備蓄米は、国家や自治体が一定量を保持している非常時用の資源です。計画的に入れ替え(ローテーション)されるため、放出される量も定期的ですが、一般消費者が自由に買えるような在庫数ではありません。仮に10万トンの備蓄があっても、放出されるのはそのうちの一部、さらにその中から業務利用や加工用途に多くが回ります。
たとえば、災害食メーカーや給食業者、大手飲食チェーンなどが大量に仕入れる場合、そもそも私たちの手に届く前に在庫がなくなるのです。ごく一部で「備蓄米〇〇kg入りが通販で販売された!」というケースもありますが、それはごく短期間・限定数にすぎず、あっという間に完売してしまうのが現実です。
このように、放出米は一見「市場に出回っている」ように見えても、消費者の手元に届く機会はほんの一握り。そのため、「どこにも売っていない」と感じるのも無理はありません。
小売が仕入れない理由とは?
スーパーやドラッグストアで「長期保存米」や「非常食セット」が販売されていることはありますが、「放出備蓄米」が並ぶことはめったにありません。これは小売店があえて仕入れないことが大きな理由のひとつです。
なぜなら、放出米には次のような特徴があります:
- 古米・古古米であることが多く、風味や食感が劣る
- パッケージが簡素で、販促しづらい
- 消費期限が短く、在庫リスクが高い
- 利益率が低く、在庫ロスになりやすい
このような商品は、スーパーのように回転率を重視する店舗には不向きです。売れ残れば廃棄コストもかかりますし、味や見た目でクレームが出るリスクもあります。
また、店舗スペースの都合上、非常食はコーナーが限られており、「売れる見込みが不確かな放出米」をわざわざ置く理由がないのです。むしろ、一般消費者に人気のあるアルファ化米や有名メーカーの防災食品の方が、販売しやすく安全だと判断されるのが現実です。
放出米は入札制度で買われている
放出される備蓄米は、ほとんどが入札制度によって販売されています。これは、「誰でも買える自由販売」ではなく、資格のある事業者が申し込んで、最も高い価格(または条件)を提示した者が購入権を得る仕組みです。
このような制度では、個人や小規模な小売業者はなかなか参加できません。さらに、入札された米は1トン単位など大ロットで販売されるため、小分け販売に向いていないのが難点です。仮に仕入れたとしても、一般消費者向けに少量で再販売するための梱包・加工・ラベル表示など、追加の手間とコストが必要になります。
このため、ほとんどの放出米は、業者がそのまま自社で利用するか、大口向けに卸すかのどちらかで終わってしまいます。
見かけない=売られていないわけではない
最後に大事なことをお伝えします。「スーパーや通販で見かけない=売られていない」とは限らない、ということです。
実際には、放出米が法人向けに流通していたり、特定のルート(JA、業務用サイト、防災イベント)などで販売されていたりします。ただし、それらは私たちが日常的にアクセスしている「生活圏内の購買ルート」には載ってこないため、気づきにくいのです。
また、最近では「ふるさと納税」などの形で提供されているケースもあり、少しアンテナを広げて探してみると、意外な場所で見つかることもあります。
つまり、放出米は“隠されている”わけではなく、“見えにくい場所にある”というのが本当のところなのです。
備蓄米を買いたいならここを探せ!
農協(JA)や道の駅、直売所をチェック
一般的なスーパーや通販サイトでは見かけない備蓄米ですが、意外な穴場が農協(JA)や地方の道の駅、農産物直売所です。これらの施設では、地元の農家や団体が地域特産のお米や保存米を独自に加工・販売していることがあり、長期保存向けのお米が手に入ることがあります。
特に、JAの直営店では地域の災害対策事業に関連して備蓄対応米を販売する例もあり、政府備蓄米とは異なるルートで流通していることも。たとえば、「5年保存用パック」や「無洗米×真空パック」といった商品が販売されているケースがあります。
道の駅などの地域施設でも、イベント時や防災フェアの期間中に「非常食コーナー」が設置されることがあり、備蓄米を含む保存食が販売されることもあります。地域限定の商品や、小ロットで製造されたアルファ化米などが見つかる可能性もあります。
ただし、これらは常時置いてあるとは限りません。事前に電話で問い合わせるか、JAや道の駅のSNSをチェックして最新情報を確認しておくのが賢明です。都会では難しくても、地方では意外と在庫が残っていることもあるので、帰省や旅行の際に立ち寄ってみるのもおすすめです。
自治体のふるさと納税サイトに注目
もし備蓄米を確実に手に入れたいなら、「ふるさと納税」を活用するのも有効な方法です。一部の自治体では、返礼品として長期保存可能な備蓄用米や、アルファ化米セット、レトルトごはんパックなどを提供しています。
たとえば、ある自治体では「災害備蓄セット5年保存」「非常用食品フルセット」などの商品が納税の返礼品になっており、家庭の防災用として使えるようパッケージされたごはん類が届く仕組みになっています。
ふるさと納税サイト(例:さとふる、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税など)で「備蓄米」「長期保存米」「アルファ化米」などのキーワードで検索すると、複数の自治体から提供されている商品がヒットします。
さらに、ふるさと納税なら実質2,000円の負担で返礼品が受け取れるため、コストパフォーマンス的にも優れています。災害備蓄と同時に、地域貢献ができるという意味でもおすすめの選択肢です。
ただし、返礼品には発送に1~2ヶ月ほどかかる場合もあるため、急ぎの備蓄には不向き。計画的に準備しておく必要があります。
防災専門ショップ・法人向け通販サイト
備蓄米を探すなら、防災用品専門の通販サイトや法人向け通販が最も確実な入手先のひとつです。ここでは、業務用のアルファ化米や長期保存用ごはんが一般向けにも販売されています。
たとえば、「セイショップ」「あんしんの殿堂 防災館」「防災グッズ通販店セレクト」などでは、政府・自治体が実際に使用している備蓄米と同等の商品が、個人でも購入可能になっています。5年~7年保存の製品、湯・水で戻せるごはん、味付きバリエーションも豊富です。
また、法人向け通販サイト(例:モノタロウ、アスクルなど)でも、事業所用の備蓄品を一般でも購入できるケースがあります。1箱10~50食入りのセットが多く、家族分をまとめて備えるには便利です。
これらのサイトでは、「定期便サービス」や「在庫復活通知」などの機能もあるため、在庫切れの商品でも再入荷のタイミングを狙って購入できる可能性があります。また、販売者が明確で安心できる点もメリットです。
フリマやオークションの注意点
どうしても入手できない場合、フリマアプリ(メルカリ・ラクマ)やネットオークション(ヤフオク)で探すという方法もあります。特に、企業や自治体が備蓄入れ替えで出品したり、防災イベントで入手した商品が転売されていたりするケースがあります。
ただし、この方法にはいくつかのリスクがあります:
- 保存状態が不明(高温多湿で保管されていた可能性)
- 賞味期限が近い、もしくは過ぎていることがある
- 高額転売(定価の2~3倍)されているケースもある
- 正規ルートではないため、品質保証が受けられない
そのため、フリマやオークションを利用する場合は、販売者の評価や商品説明をしっかり確認し、自己責任で判断することが大切です。安さに惹かれて粗悪品をつかまないよう、慎重に選びましょう。
とはいえ、「どうしても今すぐ必要!」という場合には、最終手段として検討する価値はあります。
SNSや地域掲示板の活用法
近年、Twitter(現X)やInstagram、地域の掲示板アプリ(例:ジモティー、Nextdoor)などが、備蓄米の入手情報源として非常に役立つツールになっています。
「備蓄米 入荷」「備蓄米 販売」「アルファ化米 再入荷」などのワードで検索すると、入荷速報や販売情報を投稿している人が見つかることがあります。特にTwitterでは、企業の公式アカウントがリアルタイムで在庫状況を発信していることも多く、通知をONにしておけば素早く情報をキャッチできます。
また、地域の掲示板やLINEグループなどでは、住民同士で「○○の道の駅にあったよ」「自治体イベントでもらった」などの情報が共有されることがあります。個人レベルの口コミや地元情報は、公式サイトよりも早くて役立つことが多いのが特徴です。
SNSやコミュニティをうまく使うことで、情報のアンテナを広げ、見落としていた販売チャンスをつかむことができるでしょう。
放出された米の種類と注意点
政府米・自治体米・余剰米の違い
一口に「放出された備蓄米」といっても、その種類はさまざまです。大きく分けると以下の3種類に分類されます。
- 政府備蓄米(政府米)
国が戦略的に備蓄しているお米で、主に自然災害や食料危機時に放出されます。一定期間保有された後、民間へ売却されることがあり、これが「放出」の主な対象です。 - 自治体備蓄米(自治体米)
市区町村などの自治体が、避難所や福祉施設などの非常用に保管しているお米です。こちらも使用期限や賞味期限が近づいた際に入れ替えが行われ、古いものが一部放出される場合があります。 - 余剰米(民間備蓄)
企業や団体が自主的に備えていた在庫のうち、不要になったものや更新対象となったものが市場に流れるケース。主にオークションや業務用販売ルートで出回ります。
これらはすべて「備蓄米」ではありますが、誰が保有していたか、どのルートで出回ったかによって、品質や販売条件が異なります。特に、政府米や自治体米は業務利用を前提としているため、見た目やパッケージ、味の評価が家庭用とは大きく異なることもあります。
そのため、購入時には「どのタイプの備蓄米なのか?」をしっかり見極めることが大切です。
アルファ化米とは限らない
一般的に「備蓄米=アルファ化米」と思われがちですが、実際には放出された備蓄米の多くは通常の精白米や古米であることが多いです。これは、政府備蓄や自治体備蓄が、家庭のような災害時の簡易調理を前提にしていないケースがあるためです。
アルファ化米とは:炊いたお米を乾燥させ、再び水やお湯を加えることで戻して食べられる加工米。5〜7年保存可能で、火や電気が使えない状況でも対応可能。
しかし放出された米は、こうした加工が施されていない「普通の古米」である場合が多く、炊飯が前提となっているため、非常時には使いにくい可能性があるのです。また、保存容器や脱酸素処理などの対応がされていない商品もあり、「備蓄=災害時にすぐ食べられる」という前提が崩れてしまうこともあります。
つまり、「放出=災害対応品」ではないという点に注意しなければなりません。
古米・加工用米・飼料米もある
放出された備蓄米の中には、**すでに1年以上保存された「古米」や「加工用米」、場合によっては「飼料用米」**として販売されているものもあります。
- 古米:収穫後1年以上経過したお米。乾燥が進んでおり、風味が落ちる。通常の炊飯にはやや工夫が必要。
- 加工用米:おにぎり、米粉、菓子などの加工食品向けに供給される米。精米や選別が甘いことがあり、家庭用には不向きなケースも。
- 飼料用米:家畜のエサとして使用されるグレードの低い米。基本的には人の食用には供されません。
もちろん、古米や加工用米の中にも、炊けば十分美味しく食べられるものもあります。しかし、これらはあくまで業務用途や加工業者の利用を想定しているため、パッケージ情報や賞味期限が明確でない場合も多く、個人購入にはリスクがあります。
ネットで「備蓄米」と書かれていても、実際はこうした用途のお米が含まれている場合があるため、商品説明をよく読み、出品者に確認することが重要です。
保存状態や品質を見極めるポイント
放出された備蓄米は、製造から年数が経過していることも多いため、購入前には保存状態や品質のチェックがとても重要です。特に個人販売やフリマアプリなどで手に入れようとする場合は、以下の点に注意しましょう。
- 賞味期限・精米年月日が明記されているか?
→ 不明な場合は購入を避けるべきです。 - 保存容器・パッケージが破損していないか?
→ 空気や湿気に触れていれば品質が劣化している可能性あり。 - 「無酸素包装」や「脱酸素剤入り」などの記載はあるか?
→ 長期保存を想定している場合、これが重要な基準になります。 - 保存温度が記載されているか?
→ 高温多湿で保管されていたものは虫やカビのリスクあり。 - においや色の変化がないか?
→ 開封後に明らかに異臭や変色がある場合は絶対に食べないこと。
このように、見た目や表記だけでは判断がつかないこともあるため、信頼できる販売元から購入するのが一番安全な方法です。
食用として適しているか要確認
最後に重要なポイントは、放出された備蓄米が「食用として本当に安全であるか」をしっかり確認することです。
中には、「加工用」「展示用」「試供品」などと表記された米が販売されている場合がありますが、これらは必ずしも人がそのまま食べることを想定して作られていない場合があります。安全基準が異なり、精米や異物検査も甘いことがあるため、災害時に安心して食べることができるとは限りません。
また、飼料米や破砕米などは、外観はお米でも、食用には不向きです。販売ページに「食用としての保証はありません」「自己責任で使用してください」などと記載がある商品は、備蓄目的での購入には向いていません。
安心して食べられる備蓄米を探すには、やはり防災専門店や信頼できる自治体・メーカーからの購入が一番です。値段の安さだけで選ばず、「いざという時に自分や家族が本当に口にできるか?」という目線で選ぶことが、備えとして最も大切です。
家庭で備えるならどうすればいい?
市場の流通に頼らない備蓄方法
備蓄米が放出されたとはいえ、私たち一般家庭が簡単に手に入れられるわけではないという現実がわかってきました。では、どう備えればよいのでしょうか?その答えは、**「市場に頼りすぎない、家庭主導の備蓄方法を確立すること」**です。
大切なのは、「備蓄=特別なものを買うこと」ではなく、「今あるものをうまく活用しながら、不足時に困らない状態を保つ」という考え方に切り替えること。日頃から食べている食品を多めに買い置きし、使ったら補充する、という仕組みを取り入れることで、特別な備蓄米がなくても災害時に対応できます。
スーパーで売っているお米、パックごはん、レトルト食品、乾麺、インスタント食品、缶詰など、普段使いできて保存性も高い食品は立派な備蓄品です。これらを意識的に「切らさない」ように管理することが、日常の中でできる最強の防災対策です。
また、緊急時に必要な調理器具(カセットコンロ、ガスボンベ、水タンク、ラップなど)も合わせて備えておくことで、「備蓄米がないから何もできない」となる事態を避けられます。
普通のお米を長期保存するには?
備蓄米が手に入らなくても、家庭で普通のお米を長期保存する工夫をすれば、安心して備えることができます。ただし、通常のお米は保存に注意が必要です。風味や品質を守るためには、以下のような方法が効果的です。
- 冷暗所に保管する
高温多湿はお米の大敵です。風通しがよく、直射日光の当たらない場所に保存しましょう。夏場は冷蔵庫の野菜室が最適です。 - 密閉容器や真空パックを使う
空気に触れると酸化や湿気の原因になります。密閉できる容器や、真空パック機で空気を抜いた保存が有効です。 - 防虫剤や乾燥剤を活用する
お米専用の防虫剤(天然素材の唐辛子やハーブなど)や、食品用乾燥剤を一緒に入れておくと、虫やカビのリスクを軽減できます。 - 定期的に使って入れ替える(ローリング)
半年~1年以内には使い切る前提で、少量ずつ定期的に買い足しながら備蓄するのが賢いやり方です。
これらの方法を組み合わせれば、一般のお米でも十分な備蓄が可能です。しかも、日常的に食べ慣れた味なので、災害時にもストレスが少なく安心です。
レトルトやフリーズドライごはんを活用
備蓄米の代わりに注目したいのが、レトルトごはんやフリーズドライ食品です。これらは保存性に優れ、調理も簡単で、災害時でも手軽に食事をとることができます。
特に、レトルトごはんは電子レンジや湯せんで加熱でき、保存期間は1年〜2年程度。コンビニやスーパーで手に入りやすく、備蓄しやすい商品です。「サトウのごはん」など定番商品を常に5〜10個ストックし、使ったら補充するスタイルなら、備えも簡単です。
一方、フリーズドライごはん(アルファ化米)は、5〜7年の長期保存が可能で、お湯や水を注ぐだけでふっくらごはんが出来上がります。種類も豊富で、白ごはん・わかめごはん・五目ごはん・ドライカレーなど、味のバリエーションも楽しめます。
これらを組み合わせて備蓄しておくことで、「備蓄米がなくても大丈夫」という安心感が得られます。ポイントは、「普段使うもの」と「非常用を分けて考えすぎないこと」。日常の延長として備えることが、実用的な防災対策の第一歩です。
ローリングストックのすすめ
防災の基本とされるのが「ローリングストック法」です。これは、日常的に食べている保存食品を少し多めに買い置きし、古いものから順番に使って補充していく方法です。
たとえば、レトルトごはんやカップ麺、レトルトカレー、インスタントスープなどは、普段から食べている方も多いはず。それらをいつもより2〜3個多く買っておき、使ったら新しいものを買い足すだけ。これを繰り返せば、無理なく常に「非常食」が手元にある状態をキープできます。
ローリングストックの最大のメリットは、備蓄食品が「使わずに賞味期限切れになる」ことを防げる点です。しかも、いつも食べ慣れているものだから、災害時でも安心感があり、ストレスも少ないです。
家庭の棚や収納ボックスに「ローリングストック用ゾーン」を設けておけば、誰でも簡単に始められます。ポイントは、「1食分単位」で在庫数を把握しておくこと。たとえば、家族3人×3日分=27食分を常に保管しておくなど、人数に応じた目安を決めておくと管理しやすくなります。
備えを日常に取り入れる工夫
「備蓄=災害時のためだけの特別なもの」と考えると、ハードルが高く感じてしまいがちです。ですが、実際には**「日常の中に防災を取り込む」ほうが、現実的で継続しやすい方法です**。
たとえば、以下のような工夫を取り入れてみましょう:
- パントリーやキッチン棚に「非常食ボックス」を設ける
- 毎月1日は「備蓄チェックデー」として、賞味期限を確認
- レトルト食品や缶詰を「時短料理」として活用しながら消費
- お米の買い置きを「2袋体制」にして、常に1袋はストック状態に
- 非常用持ち出し袋の中身も、季節ごとに見直す習慣をつける
また、子どもにも「非常食の日」などとして、アルファ化米や缶詰を食べる機会を設けると、災害時の「知らない不安」を減らすことができます。
このように、「備える」ことを特別なことにせず、暮らしの中に取り入れることで、自然に災害への備えができていきます。備蓄米が手に入りにくい時代だからこそ、こうした柔軟な発想が求められています。
まとめ
「備蓄米が放出された」とニュースで聞いて、「買えるようになったのかな?」と期待した方も多いかもしれません。ですが実際には、「どこにも売ってない」「スーパーにもない」と困惑する声が広がっています。
その理由は明確です。備蓄米の放出は、あくまで政府や自治体、企業などが保有する在庫を業者向けに売却する制度であり、私たち一般消費者が直接手に取れる形で流通するわけではありません。放出された米は、業務用ルートや加工用として流通し、スーパーや通販に並ぶことはほとんどないのです。
また、放出されたお米の多くは「古米」や「加工用米」であり、備蓄用のアルファ化米とは限らず、保存状態や食味に不安があるケースもあるため、購入時には注意が必要です。
では、どう備えるべきか?
それには「備蓄米がないことを前提に、自分で備える」姿勢が大切です。普通のお米を工夫して保存したり、レトルトごはんやフリーズドライ食品、缶詰などをローリングストックすることで、日常と災害時のギャップを減らすことができます。
備蓄は「買えないから諦める」のではなく、「工夫次第で誰でもできる」ものです。今回の記事を通して、現実的な備え方のヒントを見つけていただけたなら幸いです。

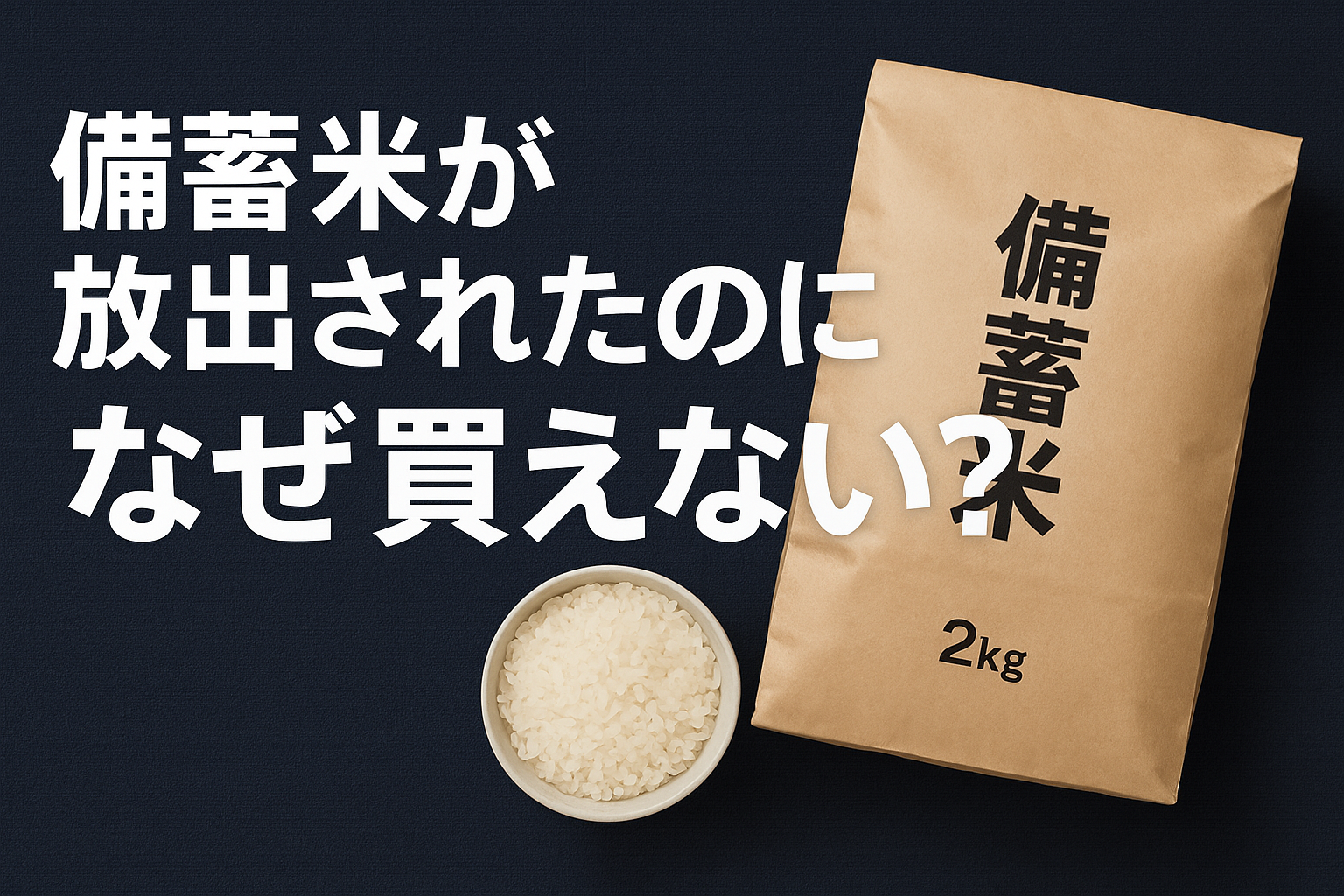
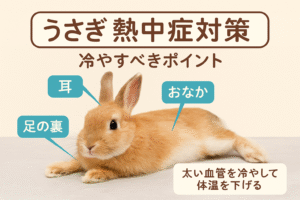

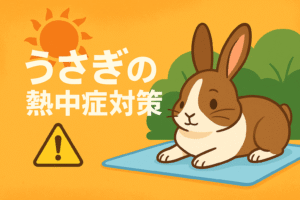
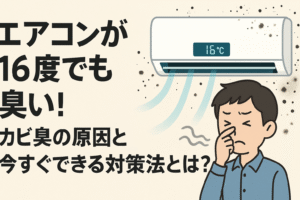




コメント