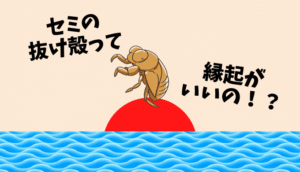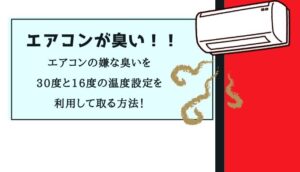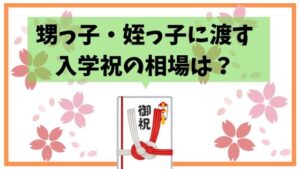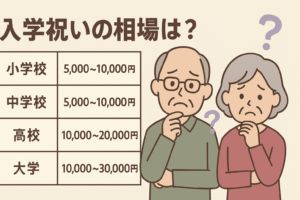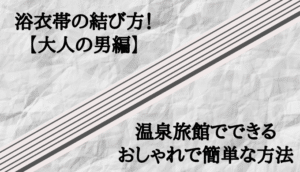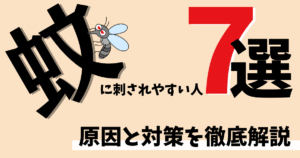「お墓参りのはしごって失礼なのかな?」「“ついで参り”はダメって聞いたけど、違いって何?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?
年に数回しかないお墓参りの機会、せっかくならマナーを守って、気持ちよく行いたいものですよね。
本記事では、お墓参りを複数まわる際の注意点や、「ついで参り」との違い、お彼岸・お盆・命日などの供養のタイミングについて、わかりやすく解説します。
これを読めば、もうお墓参りの不安やモヤモヤはスッキリ解消。
ぜひ最後まで読んで、次のお墓参りに活かしてくださいね。
お墓参りを「複数箇所」行くのはタブーなの?

お墓参りを一日に何か所かまわる、いわゆる「はしご参り」。
これをしても良いのかどうか、気になる方は多いでしょう。
結論から言えば、複数のお墓を訪れること自体は問題ありません。
むしろ、先祖を大切に想い、複数のご先祖様を訪ねる姿勢は本来、良いこととされています。
ただし、気をつけたいのは、その「気持ちの持ち方」です。
例えば「ついでにこっちも行こうか」や「近いからまとめて済ませよう」といった軽い気持ちで行ってしまうと、故人に対して失礼に当たるという考え方も根強くあります。
特に年配の方や地域の風習に厳しい方からは「心がこもっていない」と受け取られる可能性もあるため注意が必要です。
また、宗派や宗教によっては「神仏習合」を避けるべきとする考え方もあります。
仏教と神道、キリスト教など異なる宗教のお墓を同日に回ることを避ける方もおり、そうした宗教観に配慮するのも大切です。
つまり、形式よりも気持ちが大切ということ。
「今日は全員のご先祖様にご挨拶したい」という丁寧な気持ちでお参りをするなら、はしごしてもマナー違反ではありません。
ただし、体力的・時間的に余裕がある時に、心を込めて行うようにしましょう。
仏教的な観点ではどうなのか?
仏教では、ご先祖様や亡くなった方への供養の心が何よりも大切にされます。
そのため、形式的なルールよりも「敬う気持ち」を第一に考える教えが多く見られます。
お墓を一日に複数回ること自体を禁じている宗派はほとんどなく、むしろ感謝や祈りを届けたいという思いが行動に現れることを大事にするのです。
たとえば浄土宗や浄土真宗では、お念仏を唱えてご先祖の冥福を祈ることが基本です。
場所や順番にこだわるよりも、「どれだけ真心を込めて手を合わせられるか」が重視されます。
また、日蓮宗や曹洞宗、臨済宗といった禅宗でも、坐禅や読経などの修行を通して心を清め、故人を想うことが基本とされます。
ただし、地域の風習や家族内での考え方が強く影響するケースもあります。
「あの家はお墓参りを軽く見ている」といった誤解を招かないよう、仏教的な考えを知りつつも、周囲との調和を大切にすることがポイントです。
結果として、仏教の観点では「はしご参り」は問題ありません。
ただし「仏教的に問題ない=誰も気にしない」わけではないことに注意しましょう。
現実的には、人間関係や地域文化への気配りも同じくらい重要です。
神仏混合はNG?宗教ごとの違いも紹介
お墓参りの際に注意したいポイントのひとつが「神仏混合(しんぶつこんごう)」です。
日本は神道と仏教が融合した歴史を持っているため、神社とお寺、そして先祖供養が密接に関わってきました。
しかし、近代以降の宗教観では、神道と仏教の儀礼を同時に行うことを避けるべきという意識が強まっています。
たとえば、神道では死を「けがれ」と捉える考え方があり、仏教とは供養の意味が異なります。
そのため、神道のお墓(霊璽や祖霊舎)を参った後に仏教の墓地を訪れると不作法とされることも。
またキリスト教の場合は、墓参りそのものの意味や形式が異なり、花や手紙を置くことが中心になります。
一般的には、仏教墓地 → 神道墓地 → キリスト教墓地 の順に訪れる方が無難とされます。
もし同日に訪問するなら、それぞれの宗教的背景を理解したうえで、切り替えの意識を持つことが重要です。
服装も注意が必要です。
たとえば神社では帽子を取ることが礼儀ですが、寺院では必ずしもそうではありません。
「どの宗教・宗派のお墓なのか」を意識し、その教えに合わせたマナーで接することが望ましいです。
気をつけたい時間帯や順番のマナー
お墓参りをする時間帯にも気を配る必要があります。
一般的には午前中から昼過ぎまでに訪れるのが望ましいとされています。
理由は、朝の清らかな時間に手を合わせることで、故人にも失礼がないと考えられているからです。
また、日が落ちてからのお墓参りは、暗がりの中で不気味に見えることもあり、避けるのが無難です。
順番に関しては、特に決まりがあるわけではありませんが、心情的なマナーとして「本家を先に」「年長者の墓を先に」という考え方もあります。
また、親戚の中でも「嫁ぎ先」「婿入り先」をどう扱うかで意見が分かれる場合もあるため、あらかじめ家族内で相談しておくとトラブルを防げます。
さらに、神仏混合の順番(前述)や、持参するお供え物の保管・移動にも配慮が必要です。
腐りやすい食べ物は最初に置いてしまうと、次の墓地で痛んでしまう恐れがあります。
花や線香も同様に、必要な分だけ持ち歩くのが理想的です。
お墓参りは形式よりも「心の持ち方」が大切とはいえ、こうしたちょっとした気配りが、結果的に故人にも家族にも失礼にならない大人のマナーとなります。
地域差にも注意!風習の違いを知ろう
日本各地には、独自のお墓参りの風習があります。
たとえば、東北地方では「ぼんでん」と呼ばれる大きな飾りを持って墓参りをする地域もあり、関西では線香を立てずに寝かせる風習があります。
こうした違いは宗派だけでなく、土地の歴史や民俗文化に根ざしていることが多いため、非常に奥が深いです。
また、九州の一部地域では、お盆のお墓参りのあとに親戚が集まって「お墓で宴会」を開く文化もあります。
一方、関東では静かに手を合わせることが一般的で、同じ「お墓参り」でも印象がまったく違うのです。
他にも、京都ではお墓に供える花の色や並べ方に細かい作法があることもありますし、沖縄では清明祭(シーミー)という伝統的な墓前祭が春に行われるなど、地方ごとの違いに対する敬意も重要です。
旅行中や配偶者の故郷など、普段とは違う地域でお墓参りをする場合は、事前に風習を調べておくことをおすすめします。
インターネットでの情報だけでなく、地元の人に聞いてみるのも良い方法です。
「郷に入っては郷に従え」という言葉通り、その土地のやり方を尊重することが、何よりのマナーといえるでしょう。
「ついで参り」と「はしご参り」の違いとは?
お墓参りについて調べていると、「はしご参り」と並んでよく聞くのが「ついで参り」という言葉です。
この2つ、似ているようで実は大きな違いがあります。
ポイントは「お参りの優先順位」と「気持ちの込め方」です。
「はしご参り」は、複数のお墓にお参りすることを指します。
時間が限られていたり、帰省のタイミングに合わせて、一日で複数のお墓を巡るという行動です。
一見忙しそうに見えますが、ひとつひとつのお墓に丁寧に手を合わせる気持ちがあるなら、まったく問題ありません。
一方、「ついで参り」とは、たとえば「お出かけのついでに近くを通ったから」「旅行のついでに寄ってみた」といった、あくまでお墓参りが“主目的ではない”場合に使われる表現です。
つまり、お墓参りが二の次になっている印象を与えるのが「ついで参り」です。
この違いは、特に年配の方にとっては非常に大きな意味を持ちます。
「あなたは故人を大切にしているのか?」「心から手を合わせているのか?」という疑念を生むことにもなりかねません。
そのため、同じ行動でも“どういう気持ちで行ったか”が重要なのです。
時間や状況に応じて柔軟に対応するのは現代的な考えですが、それでも「お墓参りは心を込めてするもの」という基本は変わりません。
なぜ「ついで参り」がマナー違反とされるのか
「ついで参り」がマナー違反とされる最大の理由は「亡くなった方を軽んじている」と見なされるからです。
お墓はご先祖様や故人が安らかに眠る場所であり、そこに手を合わせる行為には感謝や敬意の気持ちが込められているべきです。
しかし、「ついでだから」「近くに来たから」「時間が余ったから」といった理由で訪れると、それはまるで“義務感”や“ついで仕事”のように映ってしまいます。
これは、相手を優先していない=軽視しているというメッセージに受け取られがちです。
また、お供えもせず手ぶらで立ち寄ったり、靴のまま墓石のすぐそばまで入ってしまったりと、「ついで」感覚で行動していると、無意識にマナー違反をしてしまうことも少なくありません。
さらに、こうした行為は一度でも行うと、親戚や周囲の人に不信感を与える可能性があるため注意が必要です。
お墓参りは、自分だけでなく「家」や「親族」の意識とも結びついている行為ですから、気軽に済ませようとすると思わぬ誤解や対立を生むこともあります。
結果として、ついで参りは「形式的なお参り」と受け取られやすく、マナーとしては避けるべき行為とされています。
先祖に失礼とされる心理的背景
なぜ「ついで参り」が失礼に感じられるのでしょうか。
その根底には、日本人が古くから持つ「ご先祖様を敬う心」「死者を神聖視する文化」があります。
日本では、祖先を神や仏に近い存在として大切にする風習があります。
お盆やお彼岸に家族そろってお墓参りをするのも、ご先祖様に感謝の気持ちを伝え、見守ってくれる存在として敬意を表すためです。
そんな存在に対して、「買い物の帰りに寄った」といった軽い理由で訪れることは、「真剣に向き合っていない」と感じられてしまいます。
これは、人間関係でも同じで、例えば誰かに「時間が余ったから会ってやるよ」と言われたら、あまり嬉しくはないですよね。
このように、「お墓参り=心からの敬意と感謝を伝える行為」という共通認識があるからこそ、ついで参りは失礼とされるのです。
特に年配の方々にとっては、「亡くなった方にも礼を尽くす」という価値観が強く根づいています。
形式以上に「心の在り方」を重んじる日本人らしい感性が、ついで参りに対して否定的な理由となっています。
お供えや手順に対する注意点
ついで参りのように見えてしまう原因のひとつに、「簡略化されたお参り」があります。
手ぶらで行って、手を合わせるだけ、というスタイルは気軽ではありますが、やはり故人に敬意を示すという意味では少し物足りなさを感じさせてしまうこともあります。
基本的なお墓参りの手順としては、
- 墓石や周囲の掃除をする
- 水をかけて清める
- 花やお供え物を置く
- 線香をあげて手を合わせる
この一連の流れがあるからこそ、「丁寧なお参りをしている」という印象を持ってもらえます。
とくに掃除や水かけは、故人に「会いに来ましたよ」と伝える意味でも大切な行為です。
また、お供え物にも気を配りましょう。
生ものやアルコールは禁止されている墓地もあるので、事前に確認するのが安心です。
線香も短すぎると途中で消えてしまい、意味が薄れてしまうこともあります。
要するに、「丁寧に準備して、丁寧に手を合わせる」ことで、ついで感を払拭できるのです。
急な訪問でも、せめて花や線香を持参し、掃除や水かけを欠かさないだけで印象は大きく変わります。
避けたい「NGな言動」とは
最後に、「ついで参り」と見なされやすいNGな行動についても触れておきましょう。
以下のような行動は、周囲の人や故人に対して失礼に映る可能性があります
- 手ぶらで行く(花や線香なし)
- 掃除をせずにそのまま手を合わせる
- 携帯を見ながらの片手参り
- 時間に追われてサッと済ませる態度
- 「あと1件あるから早く済ませよう」と言ってしまう
特に最後のような発言は、相手に「優先順位が低い」と思わせてしまいます。
言葉に出さずとも、態度で伝わってしまうこともあるので注意が必要です。
また、墓前での私語や笑い声も控えめに。
故人を偲ぶ場では、静かで落ち着いた振る舞いが基本です。
ついで参りにならないためには、こうしたマナーを守り、心を込めた行動を意識することが大切です。
順番はどう決める?仏教的な考え方を参考に
複数のお墓をお参りする際、どのお墓から回るべきか迷うことがありますよね。
実は、お墓参りに「絶対に守らなければならない順番」という決まりはありません。
しかし、仏教の考え方や地域の風習、家族内の暗黙の了解などをもとに、心情的に配慮された順番で回ることがマナーとされています。
よく言われるのが「本家を先に」という順番です。
これは、先祖代々の墓(本家)をまず訪れ、その後に分家や親戚の墓を訪ねるという考え方。
敬意の表れとして、本家を一番最初に訪れるという意味合いがあります。
また、亡くなった順番に基づいて訪れるケースもあります。
たとえば、祖父母の墓 → 両親の墓 → 兄弟姉妹の墓 というように、年長者から順番にお参りするスタイルです。
これも、目上の人を敬う日本人の感覚に根ざした順番だといえるでしょう。
ただし、家族や地域によって順番の考え方はさまざまです。
親族の中で何かルールがある場合は、それに従うのが一番無難です。
もし特に決まりがない場合は、「一番大切に思っているお墓」から回るのも心のこもった選択と言えます。
大切なのは、順番以上にどのお墓にも丁寧な心でお参りすること。
形式だけにこだわらず、自分なりの想いを込めたお参りが何よりも故人に届くのです。
それぞれのお墓で心を込めたお参りをするには
複数のお墓を訪ねる際、数が多いからといって「時間をかけられない」「まとめて済ませたい」と感じることもあるでしょう。
しかし、どのお墓でも「このお墓が今日の目的地」という気持ちで手を合わせることが大切です。
まず、お墓に到着したら一礼し、掃除から始めましょう。
周囲の草取りや落ち葉を拾い墓石に水をかけて清める、この「掃除する行為」自体が、すでに供養のひとつです。
「会いに来ましたよ」という気持ちを表す行動でもあります。
次に、線香を立てて合掌し、故人の名前を心の中で呼んで語りかけてみましょう。
感謝の気持ちや近況報告をするのもいいですね。
「◯◯さん、いつも見守ってくれてありがとう」そんな一言で、お参りの時間がグッと深いものになります。
また、花やお供えを置く際も、見た目の整え方に気をつけると印象が良くなります。
複数のお墓を回ると雑になりがちですが、どこでも「最初の1カ所目」と思って接することが大切です。
忙しい中でも、1カ所につき5〜10分でいいので、心のこもったお参りを意識しましょう。
それが、たとえ「はしご参り」であっても「ついで参り」とはまったく違う、真心のこもった供養となります。
合わせてやっておきたい供養の工夫
お墓参りは「現地に行くこと」だけが供養ではありません。
実は、ちょっとした工夫を加えることで、より深い供養につながることもあるのです。
たとえば、故人が好きだった花やお菓子をお供えするだけで、「あなたのことをちゃんと覚えています」という気持ちが伝わります。
こうした気遣いは、家族や親族からも「丁寧なお参りだね」と好印象を持たれやすいです。
また、写経やお念仏、お経を唱えることも立派な供養です。
時間がないときは、線香をあげる前にひと言だけ心の中でお経を唱えるだけでも十分意味があります。
最近では、スマートフォンに入れておける写経アプリや、お参りの手順をガイドしてくれる仏教アプリもあるので、それらを使って簡単にできる供養を取り入れてみるのもよいでしょう。
さらに、故人との思い出話を子どもたちに話すことも、立派な供養のひとつです。
「思い出すこと=供養」という考え方が、仏教にはあります。
お墓を通じて家族の絆が深まるようなお参りができれば、それはとても素敵な時間になるはずです。
「はしご参り」の場合のお供え物の扱い
複数のお墓を回る場合、お供え物の準備にも工夫が必要です。
すべてのお墓に花やお菓子を持っていくのは大変ですよね。
そういうときは、腐りにくいものやコンパクトな供え物を用意すると便利です。
たとえば、小さなパックに入ったお菓子や、長持ちする線香、ミニサイズの花束などは非常に重宝します。
100円ショップなどでも「墓参用セット」として便利グッズが販売されているので、事前に準備しておくと当日がスムーズです。
また、1カ所目で使った供え物を2カ所目に「使い回し」するのはマナー違反とされることもあります。
特に線香や花は、それぞれの墓に新たに用意するのが理想です。
どうしても同じものを使いたい場合でも、気持ちの面で「新たに供えるつもりで」手を合わせるようにしましょう。
飲み物やお菓子などは、墓前に長時間置くのは避けましょう。動物や虫が寄ってくる原因になります。
お供えしたあとは、感謝の気持ちを込めて持ち帰る「お下がり」としていただくのが仏教的な作法です。
供え物の扱いひとつでも、心のこもった供養になります。
せっかく複数の墓を訪ねるなら、その都度丁寧に対応したいですね。
お参り前後にしておきたい心の準備とは
お墓参りは、単なる「イベント」ではなく、自分の心と向き合う機会でもあります。
だからこそ、当日だけでなく、その前後に心の準備をすることがとても大切です。
お参りの前には、手を洗ったり、服装を整えるだけでなく、「今日はどんな気持ちで誰に手を合わせるか」を思い描いておくと、より意味のある時間になります。
また、お参りの途中でトラブルや疲れがあっても、感情的にならず穏やかに行動するよう意識しましょう。
お参りの後には、故人への感謝の気持ちをもう一度思い返し、自分の行動や気持ちを振り返ってみましょう。
場合によっては日記に「今日こんなことをお参りで感じた」と記しておくと、次回のお墓参りがより豊かになります。
心の中で「また来ますね」「いつもありがとう」と伝えるだけでも、気持ちが整理され、前向きな気持ちになります。
お墓参りは亡くなった方のためだけではなく、自分自身の人生を見つめ直す大切な時間でもあります。
忙しい中でのお参りでも、こうした心の準備と整理を意識することで、より深い意味を持つ一日になりますよ。
持ち物・服装の正解とは?
お墓参りに行く際、何を持って行くべきか、どんな服装が適切なのか、意外と悩むものですよね。
基本的に、お墓参りは改まった場であり、故人やご先祖様への敬意を表す行動であるため、持ち物や服装にも節度が求められます。
まず、持ち物については以下が基本セットです。
| 必需品 | 理由 |
|---|---|
| お花 | 故人への供養の気持ちを表す |
| 線香・ライター | 香りで場を清め、仏に祈りを捧げる |
| お供え物(果物やお菓子など) | 故人の好物や季節の物を用意する |
| 手桶・ひしゃく | 墓石に水をかけて清める |
| 雑巾・スポンジ | 墓石や周囲の掃除用 |
| ゴミ袋 | お供えの包装や掃除後のゴミを持ち帰るため |
特に最近は、持ち運びしやすいコンパクトなお墓参りセットが100円ショップやホームセンターで手に入るので便利です。
服装については、喪服で行く必要はありませんが、落ち着いた色味(黒・グレー・紺など)で清潔感のある服装が基本です。
ジーンズや露出の多い服、派手な柄物は避けるのが無難です。
足元もサンダルやヒールよりは、歩きやすく汚れてもよい靴が適しています。
夏場でもノースリーブや短パンは避け、「故人の前に立つのにふさわしいか?」を基準に選ぶと失礼がありません。
なお、冬は防寒対策も忘れずに。
寒さで集中できないと、丁寧なお参りが難しくなってしまいます。
お墓参りの持ち物と服装は、「自分の準備=故人への礼儀」という気持ちで選びましょう。
お供えものの選び方と注意点
お墓参りに持参する「お供えもの」は、故人に対する感謝や思い出を込めた大切な品です。
ただし、墓地のルールや季節によってはNGとなるものもあるため、いくつかの注意点を知っておきましょう。
まず基本となるお供えものには以下のようなものがあります。
- 季節の果物(りんご・みかんなど)
- 故人の好物だったお菓子や飲み物
- おにぎりや和菓子などの軽食
- 瓶入りのお茶やジュース
選ぶときのポイントは「常温でも傷みにくい」「動物が寄ってこない」「においが強すぎない」といった条件です。
夏場などは特に腐敗に注意しましょう。
生ものやアルコール類は墓地によっては禁止されていることも多いので、事前確認が必要です。
また、包装紙やビニール袋は外してから供えるのが基本です。
ビニールのまま置くと「仏様に心を込めていない」と感じる方もいます。
供えた後は、必ずその場で下げる(持ち帰る)のがマナーです。
食べ残しを放置すると、カラスや猫が集まり、他の墓地利用者の迷惑にもなります。
お供えは「食べてもらうもの」ではなく、「思いを届けるもの」。形式にとらわれず、故人との関係を大切にした品を選ぶことが、もっとも意味のある供養となります。
線香のあげ方と作法を確認しよう
線香をあげる行為は、仏教における供養の基本です。
煙によって心身を清め、香りを通じて故人と心を通わせるという意味が込められています。
ですが、意外と知られていないのが、宗派や地域によって線香のあげ方が異なるということです。
代表的なあげ方は以下の通りです。
| 宗派 | 線香のスタイル |
|---|---|
| 浄土宗・浄土真宗 | 寝かせて香炉に置く |
| 曹洞宗・臨済宗 | 立てて香炉に挿す |
| 日蓮宗 | 1本ずつ立てて、人数分あげることも |
まず、線香に火をつけたら、口で吹き消すのではなく手で仰いで消すのが基本マナーです。
口で吹くのは不浄とされており、特にお墓や仏壇では避けるべきとされています。
線香をあげたあとは、合掌して心の中で故人に語りかけましょう。
「こんにちは」「いつも見守ってくれてありがとう」といった自然な言葉で構いません。
仰々しく考える必要はなく、心のこもったメッセージこそが供養になるのです。
また、子どもにも線香をあげさせると良いでしょう。
火の取り扱いには注意が必要ですが、小さなうちから「お参りは大切な行為」と体験させることで、自然と供養の心が育まれます。
線香は「香りで心を届ける手紙」のようなもの。
正しい作法で、気持ちの伝わるお参りを心がけたいですね。
親戚や家族との同行時の気配りポイント
お墓参りはひとりで行くこともありますが、多くの場合は家族や親戚と一緒に行動します。
その際に気をつけたいのが、人間関係へのちょっとした気配りです。
供養は故人だけでなく、生きている家族との絆を深める機会でもあります。
まず、お墓参りの日程は事前にしっかりと共有・調整することが基本です。
勝手に予定を決めてしまうと、トラブルの原因になります。
また、高齢の親族がいる場合は、天候や移動手段、休憩場所なども考慮しましょう。
現地では、手分けして掃除や準備をすることもあります。
「自分だけ何もしない」「スマホばかり見ている」といった態度は不快に思われるので、積極的に動く姿勢が大切です。
さらに、それぞれの家族や親戚の宗教的習慣に配慮することも重要です。
線香の本数、手の合わせ方、花の種類など、細かいところで考え方が違う場合があります。
そうした時は、無理に自分のやり方を押しつけず、尊重し合うのがマナーです。
最後に、お墓参りの後に食事をするなどの予定がある場合は、故人に報告するつもりで「これから食事に行きますね」などと声をかけると、より丁寧な印象になります。
お墓参りは、家族の絆を感じる時間でもあります。
ちょっとした気配りが、思い出に残る良い一日につながりますよ。
写真を撮るのはアリ?ナシ?

最近では、SNSやブログに「お墓参りに行ってきました」と写真付きで投稿する人も増えていますが、「お墓の写真を撮るのってどうなの?」と悩む方もいるでしょう。
結論から言うと、マナーを守っていれば基本的には問題ありません。
ただし、注意すべき点がいくつかあります。
まず、故人の名前や戒名が写る写真は公開しない方が良いとされています。
個人情報の観点だけでなく、霊的な意味で「魂が写る」と嫌がる方もいるためです。
写真を撮る場合は、名前の部分を写さないか、画像加工で伏せるのが望ましいです。
また、他の墓地利用者が写り込むのもマナー違反です。
無断で人の顔が写った写真をネットに載せるのは避けましょう。
さらに、写真を撮るタイミングも大切です。
掃除や供養が終わってから、「今日も来ました」という報告の気持ちで撮影するのが良いでしょう。
お供えを並べた状態の写真は、整理整頓されていれば見た目にも美しく、記録としても価値があります。
ただし、ふざけたポーズや笑顔の写真は避けるべきです。
特にSNSに投稿する場合は、「敬意があるように見えるか」を意識しましょう。
写真撮影はNGではありませんが、供養の場としての雰囲気を壊さないよう心がけることが一番大切です。
お彼岸っていつ?どんな意味があるの?
「お彼岸(ひがん)」という言葉はよく耳にするものの、具体的な意味や時期をあいまいに覚えている方も多いのではないでしょうか?
お彼岸は年に2回、春分の日(3月頃)と秋分の日(9月頃)を中心とした前後3日間ずつ、合計7日間を指します。
この期間は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日。
仏教では、西にあるとされる「極楽浄土」とこの世が最も近づくとされ、亡き人と心が通じやすい特別な時期と考えられています。
仏教では「彼岸」は悟りの世界、「此岸(しがん)」は私たちのいる現世を意味します。
この世とあの世をつなぐ橋がかかるとも言われ、ご先祖様との絆を確かめる絶好のタイミングとされてきました。
このため、お彼岸には多くの家庭でお墓参りを行います。
日頃は忙しくてなかなか行けない人も、この時期には「家族そろってご先祖様に会いに行く」ことで、日本の伝統的な供養文化が守られています。
また、お彼岸といえば「ぼたもち(春)」「おはぎ(秋)」を供える風習もあります。
これは、あんこに使われる小豆が魔除けになるとされているためです。こうした食文化も含めて、お彼岸は「家族で思いを共有する特別な時間」なのです。
お盆のお墓参りは何をする日?
お盆(盂蘭盆会・うらぼんえ)は、毎年8月13日〜16日頃に行われる、日本でもっとも代表的な供養の行事です。多くの人が帰省し、家族でご先祖様を迎える行事として親しまれています。
仏教の教えでは、この期間に亡くなった方の霊が現世に戻ってくるとされ、家に迎え入れ、もてなしたあと、またあの世へと送り出す儀式を行います。
地方によって時期や内容は異なりますが、基本的な流れは次のようなものです。
- 8月13日:迎え火を焚いて霊を迎える
- 14〜15日:仏壇に供物をし、供養を行う
- 16日:送り火を焚いて霊をあの世へ送る
この流れの中で、お墓参りは主に13日または16日に行うのが一般的です。
墓地で迎え火や送り火を焚く地域もあり、親戚一同が集まってにぎやかに行うところもあります。
お盆のお墓参りは、単なる「手を合わせる場」ではなく、故人と再会し、語り合い、感謝を伝える年に一度の再会の時間とも言えるでしょう。
都会ではお盆期間に墓地が混雑するため、日程をずらす家庭もありますが、心がこもっていれば多少のズレは問題ありません。
できればお盆期間中に一度、故人を想って足を運びたいですね。
命日の供養はどう行うのが正解?
命日とは、亡くなった方がこの世を旅立った日のことを指します。
この日は、故人にとってもっとも大切な記念日でもあり、供養の面でも特別な意味を持っています。
命日には仏壇にお供えをしたり、読経をして故人を偲ぶ家庭が多く、可能であればお墓参りも行います。
特に「一周忌」「三回忌」「七回忌」などの年忌法要(年ごとの供養)が該当する年は、親戚を招いて法事を行うのが一般的です。
命日の供養は、お盆やお彼岸のように「全体的な行事」というよりも、個別の故人に対しての思いを届ける日です。
そのため、派手な準備や盛大な行事は不要で、静かにお参りをするだけでも十分な供養になります。
また、故人が好きだった花やお菓子を供えたり、写真に話しかけたりするだけでも供養になります。
大切なのは形式ではなく、「思い出してくれる人がいること」。それが、故人の魂を癒す何よりの贈り物です。
家庭の事情や距離的な問題で墓参りが難しい場合も、家で仏壇に手を合わせる、写経をする、好きだった音楽をかけるなど、自分にできる形で心を寄せてみましょう。
「月命日」にお参りする家庭も?その理由とは
「月命日(つきめいにち)」とは、故人が亡くなった“月日”と同じ日を、毎月の供養日とする考え方です。
たとえば3月15日に亡くなった方なら、毎月15日が月命日になります。
これは、命日を年に一度だけでなく、毎月定期的に思い出すことで心のつながりを保ち続けるという意味があります。特に、亡くなって間もない故人に対しては、この習慣を大切にしている家庭が多いです。
月命日には、仏壇にお供えをしたり、簡単なお経を唱えるのが一般的です。
近くにお墓がある場合は、短時間でもお墓参りをすることで、より深い供養となります。
また、命日が平日や忙しい日と重なってしまうこともあるため、月命日を「小さな供養のリズム」として生活に取り入れることが、現代のライフスタイルにも合っていると言えるでしょう。
心を込めたひとときを毎月持つことで、自分の気持ちも整理され、悲しみがやさしく癒されていきます。
年末年始や節目のタイミングでのお参りも大切
お彼岸やお盆、命日以外にも、節目となる日にはお墓参りをする家庭が多くあります。
たとえば、年末年始・結婚記念日・故人の誕生日など、「人生の節目を報告する」意味合いでのお参りです。
年末には「今年も一年ありがとうございました」と感謝を伝え、新年には「今年も見守ってください」とお願いする気持ちでお墓を訪れる人もいます。
こうした習慣は、家族の絆を再確認する貴重な時間にもなります。
また、合格祈願や結婚報告、出産、転職など、人生の大きな変化があったときにお墓参りをするのも、とても良い風習です。
何かを成し遂げた時、「まずはご先祖様に報告したい」と思える心は、日本人らしい美しい文化です。
節目の参拝では、特に形式にこだわる必要はありません。短時間でもいいので、故人に語りかけるように手を合わせることで、心が整い、日々の感謝も再確認できます。
お墓は「亡き人との対話の場」であり、「自分自身を見つめ直す場所」でもあります。節目節目にお墓を訪れる習慣を持つことで、より心豊かな人生を歩むことができるでしょう。
まとめ:お墓参りは「心」が一番大切

お墓参りには明確なルールがあるようでいて、実は何より大切なのは「心の持ち方」です。
数のお墓を巡る「はしご参り」自体は決してマナー違反ではなく、そこに真心があれば立派な供養となります。
一方で、「ついで参り」のように軽い気持ちや義務感だけで行うお参りは、周囲からも敬意に欠ける印象を持たれがちです。
お彼岸やお盆、命日など、日本にはご先祖様と向き合うさまざまな機会があり、それぞれに意味や背景があります。
こうした機会を大切にしながら、自分自身の生活ともバランスを取りつつ、無理のない範囲でお墓参りを続けていくことが、今の時代に合った供養の形なのかもしれません。
マナーや作法ももちろん大切ですが、形式にとらわれすぎず、「今日はご先祖様と話をする日」というシンプルな気持ちで向き合えば、おのずと良い時間になるはずです。