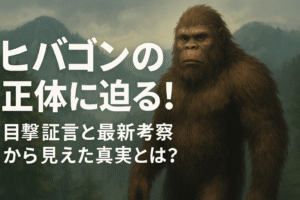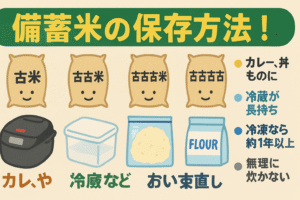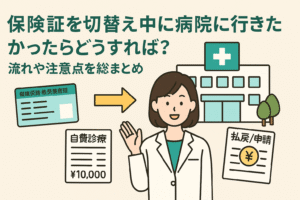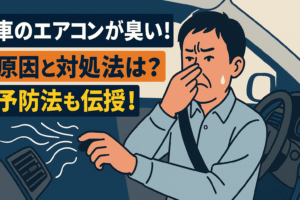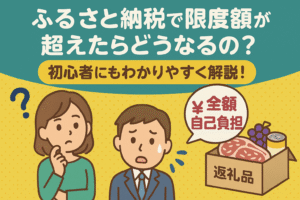2025年5月、自民・公明・立憲民主の3党が合意した「年金制度改革法案の修正」により、日本の年金制度が大きな転換期を迎えようとしています。
とくに注目されているのが「基礎年金の底上げはいつから始まるのか?」という点。
本記事では、制度の現状や政治の動き、将来的なスケジュール、そして私たちが今からできる対策まで、分かりやすく解説します。
年金に不安を感じている方、これからの生活設計を見直したい方にぜひ読んでほしい内容です。
基礎年金の底上げとは?なぜ注目されているのか
基礎年金とは何か?簡単におさらい
基礎年金とは、すべての人に共通して支給される年金で、正式には「国民年金」と呼ばれます。
20歳から60歳まで保険料を納めることで、原則65歳から満額(2025年度は月額69,308円)受け取ることができる制度です。
この制度は、すべての日本国民の老後の最低限の生活を支える「土台」として設計されています。
厚生年金とは異なり会社員や公務員だけでなく、自営業者や学生も対象です。
年金というと「将来もらえるかわからない」と不安に思う方も多いですが、基礎年金は日本の社会保障制度の中核を担う存在。
そのため、生活保護や医療保険とも密接に関わっており、単なる年金制度以上の重要性を持っています。
特に近年は非正規雇用の増加や年収が安定しない若者の増加によって「老後の最低保障」の必要性が強くなってきています。
基礎年金は、国民全体の「最低生活ライン」を守る役割を担っているため、その金額が十分かどうかは大きな関心事です。
現在の月額約69,000円では、家賃や食費・医療費を賄うには厳しいという声も多く政府は底上げを検討しているのです。
高齢化と貧困リスク:なぜ底上げが必要なのか
日本は世界でも有数の超高齢社会。
総人口の約30%が65歳以上という現状では、年金に頼る高齢者が増加し続けています。
その一方で、若者の収入は伸び悩み、年金制度を支える側の人数や収入が減少傾向にあります。
このバランスの崩れは、年金制度全体の持続性にとって大きなリスクとなっています。
また、特に深刻なのが「高齢者の貧困問題」です。
単身女性の高齢者や非正規雇用だった人々が、老後に十分な年金を得られず困窮するケースが増えています。
実際、年金だけでは生活が成り立たずアルバイトを続けたり生活保護に頼ったりする高齢者も少なくありません。
このような背景から、「基礎年金の金額が少なすぎるのでは?」という問題意識が広がっています。
生活保護との逆転現象(生活保護のほうが受給額が多い)も社会問題として指摘されており、最低保障としての基礎年金の底上げが本格的に議論されるようになったのです。
これまでの年金制度の限界
現在の年金制度は、「現役世代が高齢者を支える」という「賦課方式(ふかほうしき)」で運営されています。
この方式は、高度経済成長期のように若者が多く高齢者が少ない時代にはうまく機能していました。
しかし、現代の日本では高齢化が進み支える若者が減少傾向にあるため制度の維持が困難になっています。
さらに雇用の多様化によって正社員で長年勤める人が減少し、非正規やフリーランスが増えていることも問題です。
こうした人たちは保険料の納付が不安定になりがちで、結果的に満額の基礎年金を受け取れないことも多いのです。
制度の仕組みが今の時代に合わなくなってきていることも、改革が求められている理由のひとつです。
若年層・女性・非正規への影響
基礎年金の底上げは、高齢者だけでなく若年層や女性にも重要な意味を持ちます。
特にパートタイムで働く女性や、育児・介護でキャリアを中断した人たちは、将来的な年金額が少なくなる傾向にあります。
こうした層が老後も自立した生活を送れるようにするためには、基礎年金の底上げが必要不可欠です。
また、若年層も例外ではありません。
不安定な雇用や低賃金により保険料の納付が困難な若者も多く、将来的に十分な年金を受け取れないリスクを抱えています。
若者にとっても「底上げされた基礎年金」があることで、最低限の生活保障がされるという安心感が得られるのです。
「最低保障年金」との違いとは?
「最低保障年金」とは、基礎年金よりもさらに一歩進んだ考え方ですべての国民に一律の金額を支給することを目指した制度です。
これは、生活保護と年金の間を埋めるような制度設計で低所得者にとって非常に心強い仕組みです。
しかし、実現には巨額の財源が必要とされ国民負担が増える可能性もあるため、導入には慎重な議論が必要です。
現時点では「最低保障年金」は構想段階にとどまっており、今議論されているのはまずは現行の「基礎年金」の金額を段階的に引き上げるという方向性です。
将来的には最低保障年金の導入も視野に入っていますが、まずは「底上げ」が先決というのが現実的な議論です。
2025年5月27日、年金制度改革に関する3党合意とは
合意に至った背景とタイミング
2025年5月27日、日本の年金制度に関して大きな一歩となる合意が成立しました。
これは、与党である自民党・公明党と、主要野党である立憲民主党の3党が「年金制度改革法案の修正」に合意したというものです。
この合意は、少子高齢化の進行や年金制度への国民の不信感・将来の年金額に対する不安を背景に「最低限の生活保障を担保する年金制度への見直し」が急務とされてきた中で実現したものです。
このタイミングは、2024年から2年続けて基礎年金が引き上げられた(+2.7%、+1.9%)という事実や、次回の財政検証(2029年度)に向けて準備が進む中で、与野党が「次の一手」をどう打つか模索していたことと密接に関係しています。
特に立憲民主党が年金格差の是正と最低保障機能の強化を主張していたため、この合意は大きな意味を持ちます。
どの政党がどう関わったのか?
今回の3党合意では、自民党と公明党が中心となって策定していた改正案に対し、立憲民主党が一部修正を求め最終的に合意に至りました。
公明党は以前から「年金の底上げ」や「生活保障機能の強化」に積極的な姿勢を示しており、立憲民主党も「将来不安の払拭」を掲げて調整に臨んでいました。
与党側は、制度維持の安定性と持続可能性を重視しつつも、「最低保障的な役割」を持つ年金制度の実現には前向きな立場をとっていました。
これに対して立憲民主党は、低年金層への配慮を中心とした修正提案を行い、政策的な接点を見い出すことに成功したのです。
結果として、年金受給資格の見直し、所得再分配機能の強化、低所得者支援に関する項目の一部修正が合意されました。
合意された法案の内容(修正点)
今回合意された修正点の中で特に注目されるのが以下の3つです。
- 低年金受給者への追加給付制度の導入に向けた検討条項の追加
- 所得が一定以下の高齢者に対する年金加算の仕組み強化
- 財政検証後(2029年)を見据えた段階的制度改革の明文化
このように、ただちに年金額を引き上げるのではなく、将来的な制度変更への道筋を示したことがポイントです。
財源確保、制度の持続性、若年層への影響などを考慮し、慎重かつ段階的な見直しを基本方針としています。
基礎年金への直接的な影響は?
この法案修正によって、すぐに基礎年金が大幅に引き上げられるということはありません。
しかし、「底上げの方向性が政治的に合意された」という点が極めて重要です。
つまり、政府・与党・野党が共通認識として「現在の年金水準では不十分」であることを認め、改革に向けて具体的な土台を築き始めたという意味では、大きな一歩と言えます。
また、低所得層や年金だけでは生活できない高齢者を支援する新たな仕組みを検討することで、今後の年金制度が「最低保障」を強化する方向に向かうことが明確になりました。
今後の審議スケジュールと注目点
今回の3党合意を受けた年金制度改革法案は、2025年内の国会で正式に成立する見込みで、成立後は厚生労働省が中心となって具体的な制度設計に入り、2026〜2028年度の間に「新制度の骨子案」がまとめられる予定です。
そして、次回の財政検証(2029年度)を経て、正式な制度改正・実施に向かうというのが基本的なロードマップです。
注目すべき点は、今後の法令に「どの程度まで具体的な給付水準や対象者の範囲が盛り込まれるか」。
また、財源をどう確保するのか、若年世代に負担が偏らないかといった課題も今後の重要な論点になります。
基礎年金の底上げはいつから始まるのか?

年次調整型の増額はすでに実施中(2024年〜)
まず確認しておきたいのが、すでに実施されている「年次調整型」の基礎年金引き上げです。
これは、物価や賃金の上昇に応じて毎年自動的に年金額を見直す制度で「マクロ経済スライド」という仕組みに基づいています。
2024年度には消費者物価の上昇を受けて2.7%の増額が行われ、2025年度も1.9%の引き上げが決定しました。
つまり、この意味での「底上げ」はすでに2024年4月から始まっています。
たとえば、国民年金(基礎年金)の満額支給額は2024年度には月額68,000円台・2025年度には69,308円にまで上がっています。
これは「自動的な調整」による増額で、すでに制度の中に組み込まれているため特別な法改正を伴わずとも実施されるものです。
ただし、この仕組みはあくまで「物価や賃金の上昇に連動した微調整」にすぎず国民の期待する「大幅な底上げ」や「最低保障機能の強化」とは一線を画します。
制度改革型の底上げは「2029年度以降」が現実的
本格的な底上げ、つまり制度そのものを変えるような改革が実施されるのは2029年度以降になると見込まれています。
これは、年金制度の根幹を見直すには厚労省が実施する「財政検証」というプロセスが必要であるためです。
財政検証は4年に1度行われ、次回は2029年に予定されています。
この結果をもとに国会で改正法案が審議され、初めて制度変更が具体化します。
今回の3党合意でも制度の大幅な変更(最低保障的な制度導入や加算の仕組みなど)は「財政検証後に段階的に判断する」と明記されており、すぐに制度が変わるわけではないことが分かります。
財政検証と制度見直しの関係
財政検証とは、日本の年金制度が今後も持続可能かを予測・分析する国の重要な作業です。
厚生労働省が担当し、人口動態や経済成長・物価・賃金などの要素をもとに将来の年金水準をシミュレーションを行い、これによって年金が「どれだけ維持できるか」「どんな改革が必要か」が明らかになります。
この結果を受けて、必要であれば制度改正に着手するのが基本の流れです。
2025年に合意された内容も「2029年度の財政検証を踏まえた制度見直しを進める」という形で合意されており、年金の本格的な底上げは中長期的な計画として位置づけられていると言えます。
3党合意は実施時期にどう影響するのか
2025年5月の3党合意は、実施時期の明確化には直接的な影響を与えていませんが政治的な地ならしという意味では非常に大きな意味を持ちます。
これまで、基礎年金の底上げは「必要だが現実的に難しい」とされてきました。
しかし、与党・野党を超えて方向性が共有されたことで制度改正が「政治日程に乗った」形に。
つまり、まだ「いつから始まる」と断言できる状態ではありませんが、今回の合意によって「2029年度を起点とした本格改革の道筋が整い始めた」と解釈できます。
今後のスケジュール予測
| 年度 | 主な動き |
|---|---|
| 2025年 | 年金制度改革法案の成立、修正内容の具体化 |
| 2026〜2028年 | 厚労省による制度設計・試算作業 |
| 2029年度 | 財政検証(制度改正の前提となるデータ作成) |
| 2030年以降 | 制度改正法案の国会審議、実施可能性あり |
以上のように、今すぐに底上げが行われるわけではないが「実現可能性が高まってきた」というのが現在の状況です。したがって、「基礎年金の底上げはいつから?」という問いに対しては、
- 「毎年の調整型引き上げは2024年から実施中」
- 「制度改正による本格的な底上げは2029年度以降が現実的」
という2つの答えが存在することを明確に理解することが大切です。
具体的にいくら増える?誰がどれだけ得する?
モデルケースで見る受給額の変化
年金の「底上げ」と聞いても、実際にどれくらいもらえるのか、ピンとこない方も多いと思います。
そこで、モデルケースを使ってどれくらい年金額が変化する可能性があるのかを見てみましょう。
現在の基礎年金(満額)は、2025年度で月額69,308円(年額831,696円)です。
仮に今後制度改革によって10%の底上げが実施された場合、月額でおよそ76,200円程度(+6,900円)・年額で約91万円になります。
さらに最低保障年金の導入が進めば、基礎年金として一律月額80,000〜85,000円ほどに設定される可能性も議論されています。これは、OECDが推奨する高齢者の最低生活保障水準(相対的貧困ライン)に近づけるための金額です。
OECDは「Organisation for Economic Co-operation and Development」の略で、日本語では経済協力開発機構と訳されます。
世界中の経済や社会福祉の向上を目的とした国際機関です。
加盟国は主に先進国であり、世界経済の成長や開発、貿易の自由化などについて協議しています
こうした変化は、年金受給者の生活設計に大きく影響します。
家計の固定費が増えている今、1万円前後の増額でも非常に心強い支えになるのです。
単身女性・非正規雇用者の影響
とくに恩恵を受ける可能性が高いのが単身女性と非正規雇用で働いてきた人々です。
彼女たちは長年にわたって低賃金かつ不安定な雇用状態で働いてきたため、将来の年金が非常に少なくなる傾向があります。
たとえば、基礎年金しか受け取れないケースや、厚生年金の加入期間が短いケースです。
こうした人たちにとって、月々数千円の増額でも医療費や光熱費の支払いに大きく貢献します。
特に、70代〜80代の高齢女性の貧困率が高い現状では基礎年金の底上げは“命綱”となる改革とも言えるでしょう。
共働き世帯や専業主婦世帯の受給見通し
共働き世帯の場合、夫婦で厚生年金に加入していれば年金総額は相対的に高くなりますが、それでも基礎年金部分は一定額です。
たとえば夫婦2人で満額受給すれば、2025年度で年間約166万円。
これが10%引き上げられると、年間で約183万円になります。
また、専業主婦(第3号被保険者)として保険料を免除されながら年金を受け取る人にとっても底上げの恩恵は大きいです。
現在は夫の収入に依存する形で生活している場合が多く、自分の基礎年金が増えることは、生活の安定と老後の自立を後押しします。
高齢世代と若年世代のギャップ
一方で、今回の底上げは高齢世代にとっては朗報ですが若年世代にとっては「自分たちは本当に受け取れるのか?」という新たな不安も生じます。
なぜなら、底上げをすればその分だけ財源が必要になりそれは将来の世代が負担する可能性もあるからです。
このため、制度設計の際には「世代間の公平性」が非常に重要なテーマになります。
たとえば、将来の受給者にとってもメリットがあるように、給付の見通しや積立金の活用
税財源の使い道が透明にされなければなりません。
逆に損をする可能性はある?
注意点としては、全員が一律に得をするわけではないということです。
例えば、課税所得が増えたことで住民税や医療保険料が上がるケースも考えられます。
また、所得が一定以上の人には加算対象外になる可能性もあります。
つまり、底上げの恩恵を最大限に受けられるのは「低所得〜中所得層」であり、高所得層には影響が少ないか逆にマイナスに働く場合もあります。
さらに、制度変更時の「経過措置」や「適用開始年齢」なども重要です。
たとえば、現役世代には適用されない、あるいは段階的にしか反映されないという仕組みが導入される可能性があります。
そのため、具体的な制度内容が決まった段階で、自分がどの層に属するのかを正しく把握することが重要です。
今からできる年金対策と備え方

iDeCo(イデコ)やNISAを活用する
基礎年金の底上げが議論されているとはいえ、実際の制度改正には数年かかります。
したがって、老後の資金準備は「今から自分で始めること」が重要です。
まず注目すべきは、税制優遇があるiDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)の活用です。
iDeCoは、毎月一定額を自分で積み立て、老後に年金または一時金として受け取る制度です。
最大の魅力は、「掛け金が全額所得控除になる」点。
つまり、節税しながら老後資金を準備できるのです。
さらに運用益も非課税で受け取り時にも一定額まで税優遇があるため、長期的に見て非常に効率のよい資産形成手段といえます。
新NISAは、2024年から制度が刷新され、年間の投資上限額が大幅に拡大されました。
投資信託や株式などを非課税で運用できるため、若い世代にとっても「年金以外の柱」として期待できます。
たとえ毎月5,000円程度の少額でも、長く続ければ大きな資産に育つ可能性があるのです。
生活設計とキャッシュフローの見直し
年金対策の第一歩は、自分の生活設計を「見える化」することです。
たとえば、老後に必要な支出を項目ごとに分け、毎月の生活費がいくら必要なのか固定費や変動費をどれだけ抑えられるかをシミュレーションするのが有効です。
簡単に作れる老後キャッシュフロー表
| 年齢 | 年間支出 | 年金収入 | 不足額(貯金などで補う) |
|---|---|---|---|
| 65歳 | 240万円 | 166万円 | ▲74万円 |
| 70歳 | 250万円 | 166万円 | ▲84万円 |
| 75歳 | 260万円 | 166万円 | ▲94万円 |
※あくまで概算。住宅ローン有無や医療費により変動。
このように、将来の生活費を数値で捉えると、「どのくらい備えが必要か」「今から何をすべきか」がはっきり見えてきます。
見直しのポイントは、毎月の固定費(通信費、保険、住宅費)を無理なく削減し、少しずつでも老後資金に回すことです。
保険の見直しと医療・介護への備え
老後には医療費や介護費も増えてきます。
そのため、年金だけでは不十分な場合も多く保険の活用も有効な手段です。
ただし、保険は「入りすぎ」も「不足」も問題。
特に独身高齢者や子育てを終えた夫婦世帯の場合、死亡保険よりも医療・介護保障の手厚さが重要です。
最近は、掛け捨て型の医療保険+貯蓄という考え方が主流になりつつあります。
医療費が増えても、すぐに自己破産のような事態にはならないように公的制度(高額療養費制度、介護保険など)と連携して必要最小限の民間保険でカバーするのが賢明です。
また「就業不能保険」や「リビングニーズ特約」など、働けなくなった時の備えも検討すべきです。
公的年金がすぐには増えない以上、自衛の手段としての保険の役割は今後さらに大きくなるでしょう。
収入を増やす「セカンドキャリア」の準備
年金が足りないと感じたら、もう一つの選択肢は「収入を増やす」ことです。
定年後にアルバイトやパートで働く人が増えているのも、年金だけでは生活が厳しい現実を表しています。
しかし、どうせ働くなら「好きなこと」や「得意なこと」を活かしたセカンドキャリアとしての働き方を模索するのがおすすめです。
- 料理が得意なら料理教室講師
- ITスキルがあるなら副業プログラマー
- 手芸が好きならハンドメイド販売
上記は一例です。
近年では「シニア起業」も珍しくなく、地域の商工会や自治体がサポートしてくれるケースも増えています。
「年金以外に月3万円でも稼げれば生活に余裕が出る」というのが現実です。
早めに年金ネットやねんきん定期便で現状確認
最後に、最も手軽で重要なのが「自分の将来受け取れる年金額を把握する」ことです。
日本年金機構が提供する「ねんきんネット」では、ID登録をするだけで将来の年金見込み額や納付履歴がすぐに確認できます。
また、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」も活用しましょう。
年収や納付記録にミスがないかをチェックするだけでも、老後の準備に大きな違いが出ます。
誤った納付情報があると将来の受給額が減ってしまう可能性もあるため、早めに確認し必要に応じて問い合わせや修正申請を行うことが重要です。
まとめ:基礎年金の底上げは「始まりつつある」、本格実施は2029年以降へ

今回の記事では、「基礎年金の底上げはいつからなのか?」という疑問に対し、制度的背景、政治的合意、財政検証のスケジュールをもとに詳しく解説してきました。
現時点では、物価連動型の調整による引き上げが2024年度からすでに実施されており、2025年度も続く見込みです。
しかし、制度そのものを変えて本格的に年金の最低保障機能を強化する「底上げ」は、2029年度の財政検証を経てからの制度設計・導入が見込まれています。
2025年5月27日の3党合意によって、「方向性は定まったが、具体化には時間がかかる」というのが正確な見立てです。
これを受けて、私たち一人ひとりにできる備えは:
- iDeCoやNISAなどを活用して資産形成をスタート
- 生活設計や保険の見直しで支出を抑える
- セカンドキャリアで収入を増やす
- 年金記録をこまめにチェックする
といった具体的な対策です。
年金制度はゆっくりと、でも確実に変わり始めています。
これからの動きに注目しつつ、自分の生活を守る手段も一歩ずつ講じていきましょう。