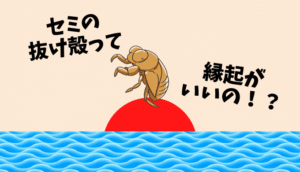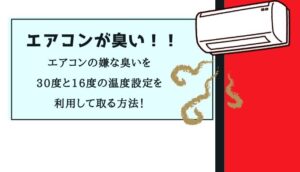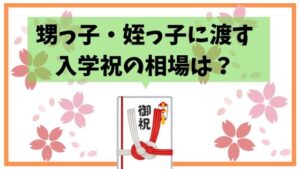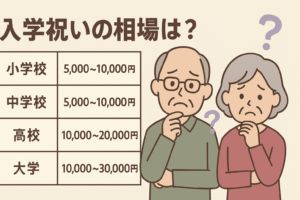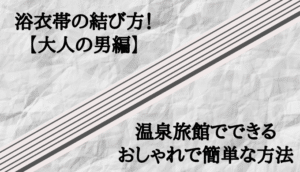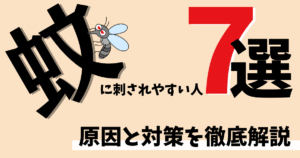夏の暑さで「なんとなく体がだるい」「食欲がない」…そんな悩み、感じていませんか?
それはもしかしたら、夏バテのサインかもしれません。
でも大丈夫。
実は、毎日の食事とちょっとした生活の工夫で、夏バテはしっかり予防・改善できるんです!
この記事では、夏バテの原因から、栄養たっぷりの食べ物選び、コンビニ活用術、そして生活習慣の見直しポイントまでをわかりやすくご紹介。
夏を元気に乗り切りたいあなたに、ぜひ読んでほしい内容です!
暑さに負けない!夏バテを引き起こす原因とは
夏バテってどんな症状?
夏バテとは、暑さによって体調を崩してしまう状態のことです。
主な症状には、食欲不振・全身のだるさ・頭痛・めまい・集中力の低下・イライラ・眠れないといったものがあります。
とくに日本の夏は高温多湿で、体にとっては非常にストレスがかかりやすい環境です。
これにより、体温調節がうまくできず、体の中でさまざまな不調が起こってしまいます。
また、夏バテの初期段階では「なんとなくだるい」「食欲がない」といった軽い不調が多いため、見過ごしがちです。
しかし、これを放置してしまうと免疫力の低下や精神的なストレスにもつながり、さらに症状が悪化することも。
軽いうちに対策を講じることが、夏バテを長引かせないポイントになります。
夏バテは体質のせいだと思われがちですが、実は生活習慣や食事内容を見直すことでかなり防げるものです。
これから紹介するポイントをしっかり押さえて、夏を元気に乗り越えましょう。
気温差と冷房がもたらすダメージ
屋外は35度、室内はエアコンで25度といったように、夏は1日の中で10度以上の気温差を経験することが多くなります。
この急激な温度差は、自律神経に大きな負担をかけます。
自律神経は体温調節や内臓の働きをコントロールしている大切なシステム。
これが乱れると、血流や消化・睡眠のリズムにも悪影響を及ぼします。
特に冷房の効いた部屋で長時間過ごすと、体が冷えてしまい、血行不良から肩こりや頭痛、胃腸の不調が起こることも。
さらに、外との温度差に体がうまく適応できず、「なんだか調子が悪い」と感じる原因になります。
冷房は設定温度を28度前後に保ち、外出時との温度差を5度以内にするのが理想です。
また、職場などで設定温度を変えられない場合は、カーディガンやひざ掛けなどで体を冷やさない工夫をすることも大切です。
胃腸の働きが落ちる理由
暑い日が続くと、つい冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎてしまいます。
すると、胃腸の中が冷えて働きが鈍くなり、消化不良や食欲不振を引き起こします。
これが夏バテの大きな原因の一つです。
また、食事の時間が不規則になったり、食欲がないからと食事を抜いてしまったりすると、胃腸のリズムが乱れてしまいます。
胃腸の働きが弱ると、栄養の吸収も悪くなり、結果として体力が落ちてさらに夏バテが進行する…という悪循環に陥ります。
できるだけ温かい食べ物を意識して取り入れ、冷たい飲み物は常温に近づけるか、せめて常温のものを選ぶようにすると良いでしょう。
また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品は胃腸に優しく、腸内環境も整えてくれるので積極的に取り入れてください。
自律神経の乱れが引き起こす不調
自律神経は交感神経と副交感神経のバランスで成り立っていますが、夏はこのバランスが崩れがちです。
日中の強い日差しや寝苦しい夜が続くことで、交感神経が過剰に働き、体がずっと緊張状態になってしまいます。
その結果、眠れない・疲れが取れない・集中できないといった不調が現れます。
さらに食欲が落ち、体力の回復も追いつかなくなるため、悪循環が続くことに。ス
トレスも自律神経の大敵なので、気分転換やリラックスする時間を取ることも大切です。
リズムのある生活を意識し、決まった時間に起きて寝る・バランスの取れた食事を摂るなど、日々の生活習慣を整えることが、夏バテ予防に直結します。
水分の取りすぎにも注意!
夏は汗をかく量が増えるため、水分補給が欠かせません。
しかし、「たくさん飲んだ方がいい」と思って冷たい水やジュースをがぶ飲みしてしまうと、かえって胃腸を冷やし、働きを鈍らせてしまいます。
これが原因で、むくみや食欲不振が悪化することも。
水分は一気にたくさんではなく、こまめに少量ずつが理想です。
また、水だけでなく、塩分やミネラルも一緒に補給できるように、スポーツドリンクや味噌汁、スープ類も上手に取り入れましょう。
食事から「食べる水分」を摂ることも夏バテ対策には効果的です。
これを食べれば元気回復!夏バテ解消に効く食べ物10選

スタミナ満点!豚肉でエネルギーチャージ
夏バテで疲れやすい時期にぴったりなのが「豚肉」です。
特に注目したいのは、豚肉に多く含まれる「ビタミンB1」。
この栄養素は、糖質をエネルギーに変えるのを助ける働きがあり、疲労回復にとても効果的です。
ビタミンB1が不足すると、エネルギー代謝がうまくいかず、疲れがたまりやすくなってしまいます。
豚肉はバラ肉やロース、ヒレなどさまざまな部位がありますが、ビタミンB1が特に豊富なのは「ヒレ肉」や「もも肉」です。
脂肪が少なく、あっさりしているので、食欲が落ちているときにも食べやすいのが特徴です。
さらに、ビタミンB1の吸収を高めるには「アリシン」と一緒に摂るのがおすすめ。
アリシンはニンニクやネギに含まれている成分で、豚肉との相性も抜群。
定番の「豚の生姜焼き」や「豚キムチ」などは、理にかなった夏バテ対策メニューといえるでしょう。
忙しい人は、冷しゃぶサラダやレンジでできる豚肉レシピなど、簡単に調理できる方法で取り入れるのもおすすめです。
食欲がなくても食べやすい!オクラのネバネバパワー
暑さで食欲がない日には、さっぱりしたものや口当たりの良い食材が重宝します。
その代表格が「オクラ」です。
オクラには独特のネバネバ成分「ムチン」が含まれており、これが胃の粘膜を保護してくれるため、弱った胃腸にとてもやさしい食材です。
ムチンはまた、たんぱく質の吸収を助ける効果もあるため、夏バテで落ちた体力を効率よく回復させてくれます。
加えて、オクラにはビタミンCや食物繊維も豊富に含まれており、免疫力を高めたり便秘解消にも役立ちます。
食べ方としては、軽く茹でて刻んで納豆や山芋と一緒に食べる「ネバネバ丼」がおすすめです。
また、冷やしうどんのトッピングにしたり、味噌汁の具としても使いやすいので、毎日の食事に手軽に取り入れられます。
下ごしらえも簡単で、さっと湯通しするだけでOK。
常備菜としても便利なので、まとめて茹でて冷蔵しておくと、時短にもなります。
ビタミンCたっぷり!パプリカやトマトで疲労回復
夏の野菜といえば「トマト」や「パプリカ」。
どちらも色鮮やかで見た目にも元気をくれるだけでなく、栄養も満点です。
特に注目したいのは、抗酸化作用の高い「ビタミンC」や「βカロテン」が豊富に含まれていることです。
ビタミンCは、ストレスを感じたときに消費されやすい栄養素で、夏の疲れやすい体には不可欠です。
また、紫外線による肌のダメージを抑える働きもあり、美容にも嬉しい効果が期待できます。
トマトには「リコピン」という強い抗酸化成分も含まれており、血流を良くして体の中から元気をサポートします。
冷やしてそのまま食べるのはもちろん、オリーブオイルと一緒に炒めたり、冷製スープ「ガスパチョ」にするのもおすすめです。
パプリカは生でも加熱しても甘くて食べやすく、サラダや炒め物にぴったり。
赤・黄・オレンジなど色とりどりなので、見た目からも食欲を引き出してくれます。
腸を整える発酵食品、納豆・ヨーグルト
腸内環境を整えることは、夏バテ予防に非常に効果的です。
そこで積極的に摂りたいのが「発酵食品」。
代表的なのが納豆やヨーグルトで、どちらも腸内の善玉菌を増やしてくれる働きがあります。
納豆にはビタミンB2や鉄分、カルシウムも含まれており、栄養バランスの面でも非常に優秀な食材です。
食欲がない朝でも、冷たいごはんに納豆をのせるだけで立派な朝食になりますし、ネギやキムチ、卵を加えてアレンジすることで飽きずに食べられます。
ヨーグルトはおやつやデザートとしても取り入れやすく、乳酸菌やビフィズス菌が腸内フローラを整えてくれます。
プレーンタイプにハチミツやフルーツを加えれば、甘さ控えめでさっぱりとしたデザートに。
冷凍フルーツと一緒にスムージーにするのもおすすめです。
腸が元気になると、免疫力もアップし、体調全体が整ってくるので、ぜひ毎日の習慣に取り入れてください。
夏でもおいしい冷やし茶碗蒸しや冷汁
暑くて熱い料理がつらい日には、「冷やし茶碗蒸し」や「冷汁」など、冷たい和食が体にやさしく、夏バテ対策にぴったりです。
冷やし茶碗蒸しは、卵とだしで作るシンプルな料理で、ツルンとした食感が食欲をそそります。
具材に鶏肉やエビ、枝豆などを加えれば、たんぱく質とビタミンが一緒に摂れるバランスの良い一品になります。
冷蔵庫で冷やしておけば、食欲がないときでもスルッと食べられます。
一方、「冷汁」は宮崎県の郷土料理で、冷たい味噌だしにごはんを入れて食べる夏の定番です。
すりごまと味噌、出汁を使った汁に、きゅうりや豆腐、シソを加えて冷やせば完成。
栄養バランスが良く、火を使わずに作れるため、暑い日でも調理が苦になりません。
このような冷たい和食は、夏バテによって弱った胃腸にやさしく、体に負担をかけずに栄養を摂ることができます。
食べ方にもコツがある!夏バテを防ぐ食事の工夫
冷たい食べ物の落とし穴
暑い日には、冷たい飲み物やアイス、そうめんなどを食べたくなる気持ちはよくわかりまが、冷たい食べ物ばかりを摂ると、内臓が冷えてしまい、胃腸の働きが鈍くなります。
その結果、消化不良や食欲不振を引き起こし、夏バテがさらに悪化することに。
冷たい物の摂りすぎは、腸の動きも弱めてしまい、便秘や下痢などの不調にもつながります。
また、体が「冷えている」と感じると、血流が悪くなり、疲れやすくなるとも言われています。
ですから、冷たい食事は1日に1回程度にとどめ、できるだけ常温や温かい食事を意識して摂るようにしましょう。
例えば、冷やしうどんよりも温かいスープや味噌汁を取り入れるだけでも、胃腸の調子が整いやすくなります。
どうしても冷たいものが食べたいときは、温かいおかずや飲み物を一緒に取り入れるなど、体全体が冷えすぎない工夫が大切です。
1日3食きちんと食べる理由
夏になると、食欲が落ちて朝食を抜いてしまったり、夜は冷たい麺だけで済ませたりと、食生活が乱れがちです。
しかし、体力を維持し、夏バテを防ぐためには「1日3食きちんと食べること」がとても重要です。
食事には、体に必要なエネルギーと栄養素を補給する役割があります。
特に朝食を抜くと、脳や体に必要なエネルギーが不足し、日中の集中力やパフォーマンスが下がってしまいます。
また、空腹時間が長くなると、次の食事で血糖値が急上昇しやすく、肥満や糖代謝の乱れの原因にもなります。
1日3回の食事をバランスよく摂ることで、血糖値の安定や自律神経のリズムも整い、体の調子がよくなります。
1回の食事が重く感じる場合は、小分けにして食べるのもOK。
おにぎりやフルーツ、ヨーグルトなどを間食として取り入れるのもおすすめです。
栄養バランスを意識しながら、できる範囲で無理なく続けられる食事習慣を心がけましょう。
朝食の大切さとおすすめメニュー
朝食は、寝ている間に消費されたエネルギーを補う大切な食事です。
特に夏場は、寝苦しい夜でエネルギーを多く消耗しているため、朝にしっかり栄養を摂ることで1日のスタートがスムーズになります。
おすすめは、炭水化物・たんぱく質・ビタミンがバランスよく摂れるメニュー。
たとえば、雑穀ごはんに納豆、冷奴、味噌汁、プチトマトなどの朝食は、簡単に準備できて栄養満点です。食欲がない日は、フルーツとヨーグルト、全粒粉のパンと卵の組み合わせも◎。
飲み物としては、冷たいジュースよりも常温の麦茶や白湯を選ぶと、体が冷えすぎずに済みます。
また、梅干しや味噌汁で塩分も適度に補えるので、汗をかく夏にはぴったりです。
朝食を習慣づけるだけで、体のリズムが整い、自律神経のバランスも良くなります。
まずは簡単なものから始めて、無理なく続けられる朝のルーティンを見つけましょう。
火を使わない簡単レシピの活用
暑い日には、キッチンで火を使うのがつらく感じるものです。
そんなときに活躍するのが、火を使わずにできる「簡単レシピ」。
手軽に作れて栄養もとれるので、夏バテ防止にもぴったりです。
例えば、「冷やしトマトのマリネ」は、トマトをカットしてオリーブオイルと塩で和えるだけで完成します。
「ツナと豆腐のサラダ」も、豆腐にツナ缶と野菜をのせ、ポン酢をかけるだけであっという間に1品になります。
電子レンジを使えば、「レンジ蒸し鶏」や「ナスのごまポン和え」なども簡単に作れます。
市販の冷凍野菜を使えば、下ごしらえの手間も省けてとても便利です。
食事の準備がストレスになると、食べる気力もなくなってしまいがちなので、手間をかけずに栄養が摂れる工夫をして、無理なく続けられるようにしましょう。
水分補給は「食べる水分」も取り入れて
水分補給と聞くと、つい「飲み物」ばかりを思い浮かべがちですが、「食べる水分」を意識するのも夏バテ対策には効果的です。
たとえば、スープ、味噌汁、果物、ゼリー、冷やし茶碗蒸しなどには水分が豊富に含まれており、体に負担をかけずに自然に水分補給ができます。
特に果物では、スイカ、メロン、キウイ、オレンジなどが水分を多く含んでいます。
ビタミンやミネラルも同時に摂れるため、夏バテで消耗しやすい体を内側からサポートしてくれます。
また、味噌汁やスープには塩分も含まれているため、汗で失われた電解質の補給にもぴったり。
冷房の効いた室内にいると喉の渇きを感じにくくなりがちなので、「のどが渇く前に食事で水分をとる」という意識が大切です。
毎日の食事の中に、無理なく「食べる水分」を取り入れることで、体が元気になりやすくなります。
コンビニでもOK!手軽に買える夏バテ対策フード
すぐ食べられる冷製パスタやおにぎり
コンビニで買える商品の中には、夏バテ対策にぴったりの食品がたくさんあります。
特に、冷製パスタやおにぎりは、食欲が落ちたときでも手軽に食べられ、エネルギーをしっかり補給できます。
冷製パスタはトマトや大葉、バジルなどを使ったさっぱり味が多く、消化にも優しいのが特徴です。
トマトのリコピン、大葉の香り成分には、疲労回復やリフレッシュ効果も期待できます。
おにぎりは、梅、鮭、昆布など、和風の具材を選べば胃腸への負担も少なく、塩分やミネラルも一緒に摂れる優秀な軽食です。
特に「雑穀米おにぎり」や「もち麦入り」など、食物繊維がプラスされたものを選ぶと栄養バランスも◎。
食欲がないときでも、冷たくて食べやすいものを選べば無理なく栄養が取れますし、何より準備不要で食べられる手軽さは大きなメリットです。
コンビニで買える発酵食品
夏バテ対策に重要な「腸内環境の改善」には、発酵食品が欠かせません。
コンビニでも、納豆、ヨーグルト、キムチ、甘酒などの発酵食品を簡単に手に入れることができます。
納豆は1パックずつ個包装されていて衛生的ですし、卵やネギ、シラスなどを加えるだけで簡単な食事になります。
コンビニによっては、すぐに食べられる「納豆巻き」や「発酵食品おかずセット」も販売されています。
ヨーグルトはドリンクタイプも多く、仕事の合間や通勤中にも手軽に摂取可能です。
砂糖不使用やプレーンタイプを選ぶと、余分なカロリーや糖分を控えつつ、乳酸菌を効率よく取り入れられます。
甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれ、アミノ酸やブドウ糖、ビタミン類が豊富。
冷やして飲めば、疲れた体に優しくエネルギーをチャージできます。
コンビニ発酵食品をうまく活用すれば、外出先でも無理なく夏バテ対策が可能です。
疲労回復に役立つドリンク類
コンビニには、夏バテ時にぴったりの栄養ドリンクや機能性飲料も数多く揃っています。
ただし、選び方には少しコツが必要です。
例えば、「ビタミンC入り」「クエン酸配合」「B群強化」といった表示があるドリンクは、疲労回復に効果的。
クエン酸は、乳酸の分解を促し、だるさを軽減してくれる働きがあります。
レモン系、梅系の飲み物によく含まれています。
また、「経口補水液(OS-1)」などは、水分・塩分・ミネラルをバランスよく補給でき、熱中症予防にも有効です。
スポーツドリンクよりも吸収率が高いため、体調不良時の水分補給におすすめです。
ただし、糖分が多い清涼飲料水は逆に体に負担をかけてしまうことがあるので注意が必要です。
なるべく無糖や低糖の製品を選ぶようにしましょう。
飲み物でも、正しく選べば食事に劣らない効果を発揮してくれます。
冷凍フルーツとカット野菜の活用
最近のコンビニでは、冷凍フルーツやカット野菜のラインナップが充実しています。
これらは手軽で調理不要、しかも栄養価がしっかり保たれているという、夏バテ対策にぴったりの食材です。
冷凍フルーツは、そのままデザートとして食べるのはもちろん、ヨーグルトやスムージーに加えることで、ビタミンや食物繊維を無理なく摂取できます。
ブルーベリー、マンゴー、いちごなどは特に人気で、冷たくてさっぱりしているため、暑い日のおやつにぴったりです。
カット野菜は、サラダ用としてドレッシングと一緒に販売されているものも多く、忙しい日でも栄養を意識した食事ができます。
パックサラダにツナやサラダチキンをトッピングすれば、立派な一食になります。
保存もしやすく、余計な手間も省けるので、ストレスなく健康を保つアイテムとして非常に優秀です。
選ぶべきコンビニ惣菜とは?
コンビニ惣菜も上手に選べば、夏バテ対策に役立ちます。
ポイントは「栄養バランス」と「消化にやさしいかどうか」です。
おすすめは、野菜が多く含まれている「お浸し」「煮物」「冷やし惣菜」、たんぱく質源としての「サラダチキン」「豆腐ハンバーグ」など。
これらは脂っこすぎず、体に負担をかけずにエネルギーを補給できます。
また、味噌汁やスープ類も見逃せません。
コンビニのスープコーナーには、具だくさんで栄養満点の商品が多く、塩分や水分の補給にも役立ちます。
反対に避けたいのは、揚げ物や脂っこいお弁当。
消化に時間がかかり、胃腸に負担がかかってしまうため、食欲が落ちているときには不向きです。
惣菜を活用するときは、「色と食材のバランス」を意識して選ぶと、体にやさしい食事が簡単に作れます。
食事以外にも注目!夏バテしないための生活習慣
睡眠の質を上げるちょっとした工夫
夏バテを防ぐには、栄養だけでなく「質の良い睡眠」も欠かせません。
しかし、夏は気温が高く、寝苦しさから睡眠の質が下がりやすい季節です。
これが続くと体が休まらず、日中の疲れが取れにくくなります。
まず大切なのは、寝室の温度と湿度の管理です。
エアコンはタイマーで入眠から3時間程度稼働させ、室温を26〜28度に保ちましょう。
扇風機を壁に向けて間接的に風を送ると、乾燥しすぎを防げます。
加えて、寝具は通気性が良く吸湿性の高い素材(ガーゼや麻など)を選ぶと、ムレにくく快適です。
また、就寝前のスマホやテレビはブルーライトによって脳が覚醒してしまうためなるべく控えましょう。
寝る1時間前には照明を落として、リラックスできる音楽を流す・軽くストレッチをするなどの「入眠ルーティン」を作ると、スムーズに眠りにつけます。
短時間でも深く眠る工夫をすることで、体力の回復力が大きく変わります。
湯船に浸かって自律神経を整える
暑い夏は、ついシャワーで済ませがちですが、夏バテ対策には「湯船に浸かること」がとても重要です。
ぬるめ(38〜40度)のお湯に10〜15分浸かることで自律神経のバランスが整い、心身ともにリラックスできます。
自律神経は、交感神経(昼間の活動モード)と副交感神経(夜の休息モード)のバランスで成り立っており、これが乱れると体調不良の原因になります。
湯船に入ることで副交感神経が優位になり、ぐっすり眠れるだけでなく、血流も良くなり疲労回復にも効果的です。
さらに、お気に入りの入浴剤やアロマオイルを使えば、香りの力でよりリラックス効果が高まります。
ペパーミントやラベンダーなど、涼しさや癒しを感じる香りがおすすめです。
忙しい日でも週に数回は湯船に浸かる習慣をつけることで、夏バテに負けない体をつくれます。
軽い運動で代謝をアップ
夏バテ対策には「軽い運動」も非常に効果的です。
運動することで代謝がアップし、血流が良くなり、体全体が活性化します。
特に、朝や夕方の涼しい時間帯に行うウォーキングやストレッチ、軽い筋トレなどが効果的です。
運動は自律神経のバランスを整えるのにも役立ちます。
ゆっくりと深呼吸しながら行うヨガや体操は、副交感神経を刺激し、リラックス効果も期待できます。
汗をかくことで体温調節機能が鍛えられ、暑さに強い体づくりにもつながります。
「毎日運動するのは難しい」と感じる人も、1日10分だけ体を動かす時間を作るだけで十分です。
エレベーターを使わず階段を使う、1駅歩く、家でテレビを見ながら足踏みするなど、生活の中で無理なく取り入れてみましょう。
運動と食事を組み合わせることで、より効果的に夏バテを防ぐことができます。
冷房の温度調整と服装の工夫
夏バテの原因の一つに「冷房による冷え」があります。
オフィスや電車、スーパーなど、外と中の温度差が激しくなることで、自律神経が乱れやすくなります。
これを防ぐには「冷房の温度調整」と「服装の工夫」がカギになります。
冷房は室温28度が目安で、湿度を下げるだけでも体感温度は下がります。
除湿機能や扇風機と併用すると、冷えすぎを防ぎながら快適に過ごせます。
職場などで設定温度を変えられない場合は、カーディガンやストールを持参して体温調節をしましょう。
特に、首元・手首・足首は「冷えポイント」とされる部分。
ここを冷やさないように意識すると、体温の低下を防げます。
エアコンの風が直接体に当たらないよう、席の位置や風向きにも気を配りましょう。
また、汗をかいた服をそのままにしておくと、体が一気に冷えてしまうので、吸湿速乾素材のインナーを着るのもおすすめです。
リラックス効果のある香りや音楽
ストレスや疲れが溜まると、自律神経のバランスが崩れ、夏バテが加速することがあります。
そこでおすすめしたいのが「香り」や「音楽」の力を使ったリラックス法です。
香りには脳に直接働きかけて気分を落ち着けたり、前向きな気持ちにさせてくれる効果があります。
例えば、ラベンダーやカモミールはリラックス効果が高く、夜のリフレッシュタイムにぴったり。
逆に、レモングラスやオレンジなどの柑橘系は、朝や仕事中に活力を与えてくれます。
アロマディフューザーやお香、ハンカチに数滴垂らすなど、手軽な方法で香りを取り入れてみましょう。
また、自然音やヒーリング音楽を聴くことで、脳がリラックスしやすくなり、睡眠の質も向上します。
YouTubeや音楽アプリで「ヒーリング」「睡眠用BGM」などを検索すれば、たくさんの選択肢があります。
こうしたちょっとした工夫で、心も体も整いやすくなり、夏バテの予防につながります。
まとめ:夏バテ対策は「食べる」「整える」で乗り切ろう!

夏バテは、暑さによって心と体が疲弊する状態で、多くの人が悩まされています。
しかし、正しい知識とちょっとした工夫で、十分に予防・解消が可能です。
今回ご紹介したように、ビタミンB1を含む豚肉や、ネバネバ食材のオクラ、ビタミンたっぷりのトマト・パプリカなど、夏にぴったりの食材を積極的に取り入れることで、体の中から元気を取り戻すことができます。
また、発酵食品で腸内環境を整えたり、冷やし茶碗蒸しや冷汁など、消化にやさしくて栄養豊富なメニューもおすすめです。
さらに、食べ方の工夫や1日3食の習慣も、夏バテを防ぐ大切な要素です。
加えて、コンビニを活用した食事法や、睡眠、入浴、軽い運動、香りの活用など、生活習慣にも少し目を向けることで、より効果的に夏バテを防げます。
「なんだか調子が悪いな…」と思ったら、無理をせず、まずは食事と生活の見直しから始めてみましょう。正しくケアすれば、暑い夏も元気に乗り越えられます!